「自社の強みが分からない人必見!自社の強みを見つけるためのヒント」
「自社の強みは何ですか?」と聞かれ、言葉に詰まる人は多いでしょう。
普段からそんなことを考えている人はあまりいないかもしれません。目の前のことに必死だからです。
自社の強みは一つの言葉から始まるのではなく、様々な要素の集合体として語られるものです。
だから、急にそう聞かれても、普段から考えていなければ、言葉に詰まってしまうわけです。
自社の強みを把握することは、事業の成長に不可欠です。
しかし、多くの企業が自社の強みを認識できていないという現実もあります。
本記事では、自社の強みを見つけるためのヒントを紹介します。
まずは、自社の個性・アイデンティティを見つけることが重要であることを解説します。
次に、自社の強みを見つけるための視点について、具体的な事例で紹介します。
例えば、既存顧客・サービスの分析や競合他社の分析を通じて、自社の強みを見つけることができます。
また、自社の特徴を把握するために、社員や顧客にアンケートを実施する方法についても解説します。
さらに、自社の強みを見つけた後に、それを活かす方法についても紹介します。
自社の強みを見つけ、競争優位性を確立するための情報が満載の記事です。
自社の強みとは何か?
自社の強みとは、他社と比べて優位に立っている点のことを指します。
つまり、お客様が自社の商品やサービスを選ぶ理由となる特徴や強みが存在していることが必要です。
例えば、他社と比べて安価でありながら品質が高い商品を提供している場合、その安価かつ高品質な点が自社の強みとなります。
自社の強みを知ることは、自社のビジネスを成功させる上で非常に重要です。
自社がどのような強みを持っているかを明確に把握することで、自社の商品やサービスをより魅力的にアピールすることができます。
また、競合他社と比較することで、自社の強みをより明確に把握することができます。
自社の強みを知ることの重要性について
自社の強みを把握することは、自社のビジネスを成功させる上で極めて重要です。
自社の強みを知ることで、自社の商品やサービスをより魅力的にアピールすることができます。
また、競合他社と比較することで、自社の強みをより明確に把握することができます。
自社の強みを知ることにより、自社のビジネス戦略を立てることができます。
自社がどのような強みを持っているかを明確に把握することで、その強みを生かすための施策を検討することができます。
また、自社の強みをより高めるための施策も検討することができます。
自社の強みの定義について
自社の強みとは、他社と比べて優位に立っている点のことを指します。
つまり、お客様が自社の商品やサービスを選ぶ理由となる特徴や強みが存在していることが必要です。
自社の強みは、その業界や市場によって異なります。
例えば、安価な商品を提供している企業では、価格がその企業の強みとなります。
自社の強みを知るための方法
自社の強みを正確に把握することはなかなか難しいです。
多くのライバルが似たような実力を持っている中で、自分たちが強みを持っていると認識するのは容易ではありません。
まずは、自分自身を客観的に見つめ直し、把握することが大切です。
自社の強みを見つけるためには、既存顧客やサービスの分析が重要な手段となります。
お客様に直接聞くことができれば理想的ですが、まずは自分たちで想像しながら自社の強みを認識することに挑戦してみましょう。
事実に基づく確認は必要ですが、まずは自分たちで仮説を立ててみます。
「仮説を立てる」とは、ある理由から推測される結果や仮定を立てることを指します。
既存顧客・既存サービスの分析
既存の顧客ニーズを深く理解することは、自社の製品やサービスの改善や市場での競争力向上につながる重要な要素です。
顧客ニーズを理解することで、顧客の満足度やロイヤリティーを高め、長期的なビジネスの継続につながることができます。
顧客のロイヤリティとは、顧客が一定期間にわたって、ある企業やブランドから提供される商品やサービスを選択し続けること、またはその企業やブランドに対して肯定的な態度を持ち続けることを指します。
つまり、その企業やブランドに対して強い愛着や忠誠心を持っている状態のことを指します。
顧客のロイヤリティが高いと、競合他社との差別化や、継続的な収益の安定化などにつながることがあります。
既存の顧客からニーズを把握するためには、顧客とのコミュニケーションを積極的に行うことが重要です。
顧客からのフィードバックを集めるために、アンケート調査やインタビュー、フィードバックフォームの導入などを行うことができます。
また、商品やサービスの利用状況の分析や、問い合わせ対応の履歴からも、顧客ニーズを把握することができます。今回の分析では、この点を省略しています。
既存の顧客から得たニーズに基づき、自社の製品やサービスを改善することで、既存の顧客からの評判を高め、口コミによる新規顧客獲得につながることができます。
また、ニーズを把握し、それに応えることで、既存の顧客のロイヤリティーを高め、リピート率の向上につながることができます。
総じて言えることは、自社の製品やサービスの改善や市場での競争力向上には、既存の顧客ニーズの理解が不可欠であるということです。
顧客とのコミュニケーションを通じて、顧客ニーズを把握し、それに応えることで、自社の製品やサービスの改善につなげることができます。
お客様は自社を選んでくれる様々な要素
既存顧客・既存サービスの分析で、なぜお客様が自社を選んでくれるのか考えるにあたり、様々な要素があります。
既存顧客が自社を選ぶ理由は多岐にわたると考えられます。
お客様が自社を選ぶ10の理由
- 高品質:製品やサービスの品質が高いため、信頼できると感じる
- 良いコスパ:価格が競合他社と比較してリーズナブルであるため、コストパフォーマンスが良いと感じる
- 豊富な種類:製品やサービスの種類が豊富で、自分に合ったものを選びやすいと感じる
- 好立地:販売店やサービス提供者の立地が便利で、利用しやすいと感じる
- 安心感:販売店やサービス提供者の対応が丁寧で、親切であると感じる
- 好み:製品やサービスのデザインやスタイルが自分に合っていると感じる
- 安全性・環境:製品やサービスの安全性や環境負荷の低さに配慮していると感じる
- 充実した情報提供:製品やサービスに関する情報提供が充実しており、自分に必要な情報が手軽に入手できると感じる
- アフターサービス:製品やサービスの長期保証やアフターサービスが充実しており、安心して利用できると感じる
- ブランド力:ブランドイメージが良く、自分が使用することで自分自身のイメージが良くなると感じる
これらの要素は、お客様が自社を選ぶ理由の一例であり、それぞれの業界や製品・サービスによって、重要な要素は異なります。
自社の強みを分析した具体例
事例1・架空の飲食店チェーン「グルメビジョン」の場合
架空の事業として、飲食店チェーン「グルメビジョン」を例に挙げます。
グルメビジョンは、全国に展開する飲食店チェーンで、和食、洋食、中華、カフェなど多彩なジャンルを提供しています。
価格帯はやや高めで、高品質な食材を使った料理と高級感ある雰囲気が特徴です。
現在、競合他社との競争が激化しており、新規顧客の獲得や既存顧客のロイヤルティ向上に取り組んでいます。
このような状況の中で、グルメビジョンは自社の強みを明確化し、ビジネス成長を図っています。
【自社の強み】
- 高品質な食材を使用し、美味しい料理を提供していること
- 高級感ある店内で、上質なサービスを提供していること
- 幅広いジャンルの料理を提供しており、顧客のニーズに応えられること
- オリジナルメニューの開発に力を入れ、他社との差別化を図っていること
- 定期的に新メニューや季節限定メニューを提供し、顧客の興味を引いていること
- 店舗展開が全国規模であり、多様な地域の顧客にアプローチできること
- チェーン展開により、経営効率化を図っており、コスト削減ができること
- ブランド力が高く、顧客に認知されていること
グルメビジョンは、自社の強みを明確にし、それを生かした戦略を展開することで、競合優位性を高め、新規顧客獲得や既存顧客のロイヤルティ向上に成功しています。
例えば、1や2の要素を生かし、高品質な食材とサービスを提供することで、高級感ある雰囲気を醸し出し、顧客のニーズに応えることができます。
また、4や5の要素を生かし、オリジナルメニューや季節限定メニューを提供することで、顧客の興味を引き、競合他社との差別化を図ることができます。
さらに、6の要素を生かし、地域ごとに異なるメニューを提供することで、地域の顧客の好みに合わせたアプローチができます。
また、7の要素を生かし、経営効率化に取り組むことで、コスト削減を実現し、価格競争力を維持することができます。
グルメビジョンは、自社の強みを活かしつつ、顧客ニーズの変化や競合他社の動向に対応することで、事業成長を継続しています。
例えば、近年では健康志向の高まりに伴い、ヘルシーメニューの提供や食材の産地表示など、より健康に配慮した取り組みを行っています。
また、テイクアウトやデリバリーサービスの導入など、時代の流れに合わせた新たなサービス展開も行っています。
こうした取り組みにより、グルメハウスは新規顧客の獲得や既存顧客のロイヤルティ向上を実現し、事業成長を継続しています。
事例2・架空の営業コンサルティング会社「ナイン・カルテル」の場合
設計事務所、会計事務所、税理士事務所、個人ジム運営などのように、無形のサービスを提供している業態もあります。
営業コンサルティング会社「ナイン・カルテル」を例に挙げます。
ナイン・カルテルは、企業経営者や経営幹部を対象にした営業コンサルティングを提供する会社です。
顧客のニーズに合わせた効果的な営業戦略の策定や、経営戦略の改善・強化などを行っています。
価格帯はやや高めで、顧客に高い付加価値を提供することを目指しています。
現在、競合他社の増加により、新規顧客の獲得や既存顧客のロイヤリティ向上に取り組んでいます。
【自社の強み】
- 高い専門性と豊富な経験に基づく高品質なコンサルティングサービスを提供していること
- 顧客のニーズに合わせた効果的な営業戦略の策定や、経営戦略の改善・強化ができること
- 専門家チームによるコンサルティングサービスを提供しており、多様なニーズに対応できること
- 独自のビジネスモデルを持ち、競合他社との差別化を図っていること
- 定期的なアフターフォローやサポート体制が整備されており、顧客満足度を高めていること
- ブランド力が高く、多くの企業経営者や経営幹部からの信頼があること
ナイン・カルテルは、自社の強みを活かして、顧客ニーズに合わせた高品質なコンサルティングサービスを提供することで、競合優位性を高め、新規顧客獲得や既存顧客のロイヤリティ向上に成功しています。
例えば、1や2の要素を生かし、高い専門性と豊富な経験に基づく高品質なコンサルティングサービスを提供することで、顧客のニーズに応えることができます。
また、4の要素を生かし、独自のビジネスモデルを持つことで、競合他社との差別化を図るこことができます。
さらに、3の要素を生かし、専門家チームによるコンサルティングサービスを提供することで、多様なニーズに対応することができます。
また、5の要素を生かし、定期的なアフターフォローやサポート体制を整備することで、顧客満足度を高め、既存顧客のロイヤリティ向上に取り組んでいます。
ナイン・カルテルは、常に顧客ニーズに合わせた高品質なサービス提供を心がけ、定期的な調査や分析を行うことで、事業成長を継続しています。
例えば、近年ではデジタル化やグローバル化に対応するため、オンラインコンサルティングや海外展開支援など、新たなサービス展開を行っています。
こうした取り組みにより、ビジネスアドバイザーズは顧客から高い評価を受け、業界のリーディングカンパニーとしての地位を確立しています。
事例3・架空のクリーニング店「ふわふわクリーニング」の場合
前の2つの事例は、高いレベルの商品を持っているという点で、分析が容易であったかもしれません。
次に、品質は平均的、特に突出しておらず、細くながく事業を展開してきた架空の事例についてあげてみます。
普通の分析をしてもそんなに違いがないけど、なぜか細くとも長いおつきあいをしていただいているお客様がいて、事業が続けてこられた場合です。
よくよく分析したら、視点を変えることでこれらは強みだったんじゃないかと、自分でも驚くような発見が見つかる場合があります。
架空の事例として、地元密着型のクリーニング店「ふわふわクリーニング」を例に挙げます。
ふわふわクリーニングは、地元の住民を中心にクリーニングサービスを提供している小規模なクリーニング店です。
商品やサービスの品質は平均的で、価格も競合他社と同様の水準です。
しかし、長年にわたり地元の住民に愛され、多くのリピート顧客を抱えています。
【自社の強み】
- 地元密着型であることによる顧客との繋がりの強さ
- 長年にわたる地元住民からの信頼や口コミによる集客力
- オーナー自身が店舗で接客やクリーニング作業を行っていることによる顧客満足度の高さ
- クリーニングの品質は平均的であるが、特定のニーズに対応できる柔軟性があること
- オーナーの人柄により、親近感や信頼感を感じることができること
ふわふわクリーニングは、自社の強みを活かして、地元密着型のサービスを提供することで、地元住民に愛されるクリーニング店として、多くのリピート顧客を獲得しています。
例えば、1の要素を生かし、地元密着型であることによる顧客との繋がりの強さを活かし、地域イベントやチラシ配布など、地元住民とのコミュニケーションを大切にしています。
また、4の要素を生かし、特定のニーズに対応できる柔軟性を活かし、特殊なクリーニングの受付や、顧客からのリクエストに応えたクリーニングを行っています。
ふわふわクリーニングは、視点を変えることで、自社の強みを発見し、地元密着型のクリーニング店として、多くのリピート顧客を抱えています。
例えば、5の要素を生かし、オーナーの人柄による親近感や信頼感を生かし、顧客とのコミュニケーションを大切にすることで、地元住民からの口コミや紹介による新規顧客の獲得にもつながっています。
また、2の要素を生かし、長年にわたる地元住民からの信頼や口コミによる集客力を生かし、地元の自治体や商店街との協力体制を築くことで、地域の活性化にも貢献しています。
このように、自社の強みを見つけるためには、商品やサービスの品質だけでなく、地元密着性や顧客満足度など、様々な視点から分析する必要があります。
架空の事例である「ふわふわクリーニング」でも、商品やサービスの品質が突出しているわけではありませんが、地元密着型であることや、オーナーの人柄による顧客との繋がりの強さなど、自社の強みを発見することができました。
自社の強みを分析することは、事業を長期的に展開していくために必要な取り組みの一つだと言えます。
特に何かが突出しているというわけではなく、製品やサービスが平均的であっても、その提供の仕方の工夫でお客様に選ばれているということがわかり、改めて自社サービスを認識することができた事例になると思います。
自社の強みを見つけることで、自社サービスをより良くするための改善点を見つけることができますし、競合他社との差別化にもつながります。
自社の強みを分析した「ふわふわクリーニング」はどうなる?
変化する環境に対応する場合
極端な話ですが、「ふわふわクリーニング」のオーナーさんは、今のままでも良いと思いながらも、この先続けていけるか不安も抱えています。
高齢化社会に突入したり、様々な環境変化が予測されます。
環境変化をいくつか想定し、どう対応していくか想像してみたいともいます。
ゴールは、今の売上が維持できればというものです。
想定される環境変化としては、以下のようなものが考えられます。
- 環境意識の高まりによるエコクリーニング需要の増加
- スマートフォンの普及によるネット通販やデジタル決済の普及
- 新型コロナウイルス感染症の影響による外出自粛や非接触型サービスの需要増加
これらの環境変化に対して、以下のような対応策が考えられます。
- 環境意識の高まりによるエコクリーニング需要の増加 「ふわふわクリーニング」は、地域密着型のクリーニング店として、環境負荷を抑えたエコクリーニングを推進することができます。
例えば、環境に優しい洗剤や洗浄機器の導入や、再利用可能なエコバッグの提供などが挙げられます。
また、クリーニングに限らず、生活用品の修理やリメイクサービスなども提供することで、お客様の環境意識に対応した幅広いサービス提供が可能となります。 - スマートフォンの普及によるネット通販やデジタル決済の普及 スマートフォンやネット通販が普及した現代においては、デジタル化したサービス提供が求められます。
例えば、ネット予約やオンライン決済、SNSを活用した情報発信や顧客とのコミュニケーションなどが挙げられます。
また、スマートフォンアプリの開発や、ポイントサービスの導入なども検討することで、お客様に便利なサービス提供を行うことができます。 - 新型コロナウイルス感染症の影響による外出自粛や非接触型サービスの需要増加 新型コロナウイルス感染症の影響により、外出自粛や非接触型サービスの需要が増加しています。
そのため、「ふわふわクリーニング」でも、オンライン予約や宅配クリーニングなどの非接触型サービスを提供することが重要です。
また店舗内の感染症予防策として、定期的な換気やアルコール消毒、マスク着用の徹底なども必要です。
さらに、店舗内の物理的な距離を保つために、入店制限や待ち時間の設定なども検討することで、お客様に安心してご利用いただける環境を整えることができます。
以上のように、様々な環境変化に対応するためには、自社サービスのデジタル化や非接触型サービスの提供、環境負荷の低減など、多角的な対策が必要です。
また、お客様に対しては、自社サービスの提供価値をアピールすることが重要であり、そのためには、強みの分析や顧客ニーズの把握なども重要となります。
世代交代・事業拡大に舵を切る場合
もう一つ、別のストーリーを考えてみたいと思います。
「ふわふわクリーニング」を継いだ長男は、事業を拡大させていきたいと考えていたとします。
3年程度を目途に、事業拡大をしていくにあたり、現状分析、事業拡大策をどのような考えるかというストーリーを考えてみました。
「ふわふわクリーニング」を拡大させるためには、まず現状の分析が必要です。具体的には、顧客層の把握や需要の把握、競合他社の分析、店舗の効率化や生産性の向上などを行う必要があります。
顧客層の把握と需要の把握については、データを収集することが重要です。
例えば、利用者の年齢層や性別、居住地域、利用頻度などの情報を把握し、需要の高いサービスや商品を把握することができます。
また、リピート率の向上や新規顧客の獲得に向けて、マーケティング戦略の見直しも必要です。
競合他社の分析については、競合他社の強みや弱みを把握することが重要です。
特に、弱みを見つけ出して、自社の強みをアピールすることができると、顧客の獲得につながる可能性があります。
店舗の効率化や生産性の向上については、自動化やIT化、設備の改善などを行うことで、より効率的な業務フローを実現することができます。
また、人材育成や組織風土の改善なども、生産性の向上につながります。
以上の現状分析を踏まえて、事業拡大策を考えることが重要です。
具体的な事業拡大策としては、新規店舗の出店や、提携先との協業などが挙げられます。
また、オンラインショップの開設や配送サービスの充実、新しい商品の開発なども、事業拡大につながる可能性があります。
ただし、事業拡大にあたり、リスク管理も重要です。
経営資源の配分や財務状況の把握などを十分に行い、リスクを最小限に抑えた上で、事業拡大を進めることが重要です。
顧客層の把握と需要の把握については、データを収集することが重要です。
例えば、利用者の年齢層や性別、居住地域、利用頻度などの情報を把握し、需要の高いサービスや商品を把握することができます。
また、リピート率の向上や新規顧客の獲得に向けて、マーケティング戦略の見直しも必要です。
競合他社の分析については、競合他社の強みや弱みを把握することが重要です。
特に、弱みを見つけ出して、自社の強みをアピールすることができると、顧客の獲得につながる可能性があります。
長男は、どう分析して、どう考えたか
長男はまず、顧客層の把握と需要の把握について、データを収集することを考えました。
具体的には、店舗内でのアンケート調査や、会員制度の導入、SNSなどの情報収集ツールを活用することを考えました。
また、これらのデータを分析することで、需要の高いサービスや商品を把握することができます。
例えば、若年層に人気のある特殊な洗剤を導入したり、独自のアレンジサービスを提供することで、差別化を図ることを考えました。
次に、競合他社の分析については、インターネットや地域の情報誌を活用して、競合他社の強みや弱みを把握しました。
そして、競合他社の弱みを見つけ出して、自社の強みをアピールすることで、顧客の獲得につながる可能性があることに気付きました。
例えば、競合他社が24時間営業していない場合、自社が24時間営業していることをアピールすることで、需要の獲得につなげることができます。
また、新規顧客の獲得については、オンラインショップの開設や配送サービスの充実、新しい商品の開発なども検討しました。
例えば、オンラインショップの開設によって、地理的な制限を超えて需要を獲得することができます。
また、新しい商品の開発によって、需要の開拓を図ることもできます。
ただし、事業拡大にあたり、財務面やリスク管理についても十分に考慮する必要があります。
長男は、事業拡大にあたり、財務面やリスク管理についても綿密に計画し、最適な経営戦略を模索することを決めました。
まとめ
以上、急に聞かれても答えることが難しい「自社の強み」について説明してきました。
・今のお客様がなぜ自社を選んでくれるのかを考えることで、自社の強みを見つけることができます。
・自社の強みを把握することで、将来の事業展開について考えることができることを説明しました。
自社の強みを分析することの重要性について
自社の強みを正確に把握することは、競争激化するビジネス環境で生き残るために不可欠な取り組みです。
自社の強みを見つけることで、自社サービスを改善するための改善点を見つけることができますし、競合他社との差別化にもつながります。
お客様にとっても、自社の強みを理解することで、より適切なサービス提供や商品選択ができるようになります。
自社の強みを分析することは、事業を長期的に展開していくために必要な取り組みの一つであり、ビジネスの成功に不可欠です。
強みを見つけるための方法とその活用方法について
自社の製品やサービスが、成功とまでは言えず、平均的な状況である場合には、以下のような仮説を立てることができます。
- 競合他社との差別化⇒市場での存在感を高める
自社の製品やサービスが平均的な場合は、競合他社との差別化が必要となります。
例えば、価格競争に巻き込まれず、高品質やデザイン性、サポート体制の充実など、他社とは異なる付加価値を提供することができます。 - 顧客ニーズを深く理解&自社の製品やサービス強化⇒市場での需要拡大
自社の製品やサービスが平均的な場合は、顧客のニーズを深く理解し、自社の製品やサービスを改善することが必要となります。
例えば、顧客とのコミュニケーションを活発に行い、顧客からのフィードバックを反映した製品やサービスを提供することができます。 - 新しいビジネスモデルを模索する⇒市場での成長戦略を実現
自社の製品やサービスが平均的な場合は、新しいビジネスモデルを模索することで、市場での成長戦略を実現することができます。
例えば、既存の市場に飽和状態が見られる場合には、新しい市場を開拓することが必要となります。
以上のような仮説を立て、それを検証するために、市場や顧客の調査、競合他社との比較分析、社内外でのアンケート調査など、様々な情報収集を行うことが重要です。
また、自社の強みや弱みを洞察し、自社が提供する付加価値を明確にすることも重要です。
仮説を立て、それを検証することで、自社の製品やサービスの改善や市場での競争力向上に繋がると考えられます。




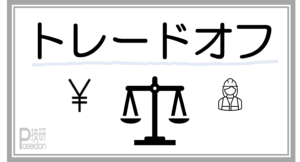
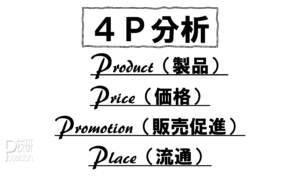





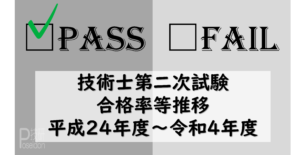
コメント