

語句説明&まとめ:総合技術監理
語句説明&まとめ:経済性管理
語句説明&まとめ:人的資源管理
語句説明&まとめ:情報管理
語句説明&まとめ:社会環境管理
PCで見ていただくと目次が追いかけてきてくれます。
技術士会の総合技術監理キーワード集 (mext.go.jp)を見ながら、検索していただくことも可能です。
技術士の総合技術監理部門は、広範な知識とスキルを必要とする分野です。
しかし、そのカバー範囲についての公式書籍である通称・青本の配布が終了したので、
情報の更新も無くなってしまいました。。
今は、技術士会の総合技術監理キーワード集 (mext.go.jp)だけが毎年配られていますが、キーワードの解説については情報がありません。
自分で調べましょうということになっており、その量は膨大です。
そこで、日本技術士会から提供されたキーワードを使って、内容について調べてみました。
ここでは、私が調べた内容を、皆さんと共有したいと思います。
これを使うことで、技術士の総合技術監理部門についての理解を深め、自分自身のスキルアップに役立てることができます。
情報が不足しているところもありますが、調べるきっかけになればと思います。
情報は随時更新していきますので、よろしくお願いいたします!
5.1 安全の概念
(総監キーワード2023より抜粋)
従来の安全管理では,労働安全衛生に関する取り組みや,火災や爆発などの個別被害形態毎に未然防止対策を検討することが中心であった。
しかし近年,IoT導入などによりさまざまなものやシステム,組織,社会などが相互に関係を深め,企業等における安全の問題は,組織構造,マネジメント,工学技術,パンデミックも含めた社会環境などに大きく依存するようになった。
そのため,安全管理は,個別に細分化した安全対策を実施するだけでなく,組織全体のマネジメントの問題として取り組むことが必要となってきている。
また,カーボンニュートラルやDX等の社会の変化が安全の問題や対応にも大きな変化をもたらすことにも注意すべきである。
本節では,安全の概念や安全に関わる制度・システム,およびそれへの対応の考え方などを扱う。
安全マネジメント
安全マネジメントは、組織内の安全を管理するための総合的なアプローチです。
安全マネジメントには、危険を評価し、リスクを分析し、適切な対策を講じることが含まれます。
このプロセスは、定期的な監査や評価を通じて改善されます。
安全マネジメントシステム
安全マネジメントシステムは、組織が安全マネジメントを実施するための体系的な手法であり、ISO 45001のような標準に基づいています。
安全マネジメントシステムは、安全目標や指標を設定し、継続的な改善を行うことで、組織内の安全を確保します。
安全管理
安全管理は、組織内の人々や設備、プロセスなどを管理し、安全な作業環境を維持するための活動です。
安全管理は、定期的な監査や評価、事故調査などを通じて、組織内の安全性を継続的に向上させます。
安全管理システム
安全管理システムは、安全管理を実施するための体系的な手法です。
ISO 45001などの標準に基づいています。安全管理システムは、安全管理計画の策定、実施、評価、改善を通じて、組織内の安全性を確保します。
安全目標
安全目標は、組織が目指す安全に関する具体的な目標です。
安全目標は、組織の方針や目的を反映しており、組織内の全員が共有するべきです。
安全経営
安全経営は、組織の経営層が安全を組織戦略の一環として扱うことです。
安全経営は、安全マネジメントや安全管理を強化し、組織内の安全意識を高めることが目的です。
安全投資
安全投資は、組織が安全性を確保するために投じる資金やリソースです。
安全投資は、安全管理システムや設備の改善、教育訓練の実施、安全文化の醸成などに用いられます。
安全投資は、事故発生や法的な問題を回避するためにも重要です。
社会安全
社会安全は、社会全体の安全性や平和を守ることを目的とする概念であり、犯罪やテロ行為、自然災害、公衆衛生の脅威など、多岐にわたる危険に対処することを含みます。
防災
防災は、災害が発生した場合に備え、人命や財産を守るための活動です。
具体的には、災害リスクの分析、避難計画の策定、避難所の整備、防災教育の実施などが挙げられます。
レジリエンス
レジリエンスは、自然災害やテロ攻撃などの危機に対して、素早くかつ適切な対応を行い、その後の復旧や再生に向けた力強い回復力を備えることを指します。
レジリエンスを高めるためには、危機管理の能力や社会的な結束力を強化する必要があります。
レジリエンス(resilience:日本語での直訳は「回復力、弾力性」です。)とは、環境の変化やストレスなどの外的刺激に対して、回復力や耐性を持ち、元の状態に戻る力や能力のことを指します。
レジリエンスは、物理的な耐久性だけでなく、精神的な強さや柔軟性、適応力なども含みます。
例えば、自然災害や経済危機などの困難な状況に直面した場合、個人や組織がレジリエントであれば、状況に応じた適切な行動をとり、回復や再生を目指すことができます。
レジリエンスは、個人や組織、地域社会など様々なレベルで考えられる重要な概念です。
オールハザードアプローチ
オールハザードアプローチは、あらゆる種類の災害や危機に対処するための包括的なアプローチです。
オールハザードアプローチでは、自然災害やテロ攻撃、感染症などのあらゆる種類の危険を想定し、災害リスクの評価や防災対策の策定を行います。
公衆安全
公衆安全は、市民の安全と健康を保護することを目的とする概念であり、食品衛生や環境衛生、感染症の予防、治安維持などが含まれます。
消費者安全
消費者安全は、製品やサービスの安全性を確保することを目的とする概念であり、製品の設計・製造・販売段階での安全性評価や消費者への情報提供、製品リコールなどが含まれます。
利用者安全
利用者安全は、医療や介護、福祉サービスなどの利用者の安全性を確保することを目的とする概念であり、医療事故の防止や感染症対策、利用者の権利保護などが含まれます。
事業安全
事業安全は、企業活動における危険やリスクを評価し、事業継続に必要な安全性を確保することを目的とする概念です。
例えば、産業事故や環境汚染などを防止するための安全管理が含まれます。
プロセス安全
プロセス安全は、化学プラントや製造工場などのプロセスにおいて、事故や災害を防止するための安全性を確保することを目的とする概念です。
プロセス安全には、プロセスハザード分析やリスクアセスメント、設計やメンテナンスにおける安全性評価などが含まれます。
プロセスセーフティマネジメント(PSM)
プロセスセーフティマネジメント(PSM)は、プロセス安全を実現するための管理システムであり、米国労働安全衛生局(OSHA)が規定する規制の一つです。
PSMには、プロセスハザード分析、安全性評価、手順書作成、トレーニング、監査、改善などが含まれます。
PSMは、「Process Safety Management(プロセスセーフティマネジメント)」の略で、プロセス安全を実現するための管理システムの一つです。
OSHAは、「Occupational Safety and Health Administration(労働安全衛生局)」の略で、アメリカ合衆国の労働安全衛生に関する規制当局です。
システム安全
システム安全は、製品やサービスの設計や運用において、人や環境への影響を最小限に抑えるための安全性を確保することを目的とする概念です。
システム安全には、ハードウェア・ソフトウェアの設計や評価、運用上のリスク管理などが含まれます。
RBM(リスクベースメンテナンス)
RBM(Risk-Based Maintenance)は、設備のメンテナンスにおいて、リスクに基づいた優先順位でメンテナンスを行う手法です。
RBMでは、設備の重要度やリスクに応じて、メンテナンスの頻度や方法を決定します。
RBI(リスクベース検査)
RBI(Risk-Based Inspection)は、設備の点検・検査において、リスクに基づいた優先順位で検査を行う手法です。
RBIでは、設備の重要度やリスクに応じて、検査の頻度や方法を決定します。
サイバーセキュリティ
サイバーセキュリティは、情報システムやインターネットにおける情報資産を保護するための安全対策です。
サイバーセキュリティには、情報セキュリティポリシーの策定、システムの設計や運用、ネットワークの防御策、ユーザーの教育・訓練などが含まれます。
近年では、クラウドサービスやIoT機器などの普及に伴い、サイバーセキュリティの重要性が一層高まっています。
労務安全衛生
労務安全衛生は、職場における労働者の安全と健康を保護するための活動です。
具体的には、職場での事故や疾病の予防、安全教育や訓練、安全機器の整備などが含まれます。
製品安全
製品安全は、製品が人や環境に与える影響を最小限に抑えるための安全対策です。
具体的には、製品の設計や製造、販売前の評価、取り扱い方法の表示などが含まれます。
製品安全は、消費者や利用者の安全性を確保するために重要です。
事業継続計画(BCP)・事業継続マネジメント(BCM)
事業継続計画(BCP)は、災害や危機に備え、事業を継続するための計画です。
BCPには、事業の継続性評価、業務プロセスの分析、復旧手順の策定、教育訓練の実施などが含まれます。
また、BCPの実施にあたっては、組織内での役割分担や情報共有の体制整備なども必要です。
事業継続マネジメント(BCM)は、BCPを実施するためのマネジメントシステムです。
BCMには、災害リスクの評価やビジネスインパクト分析、復旧計画の策定、継続的な評価や改善などが含まれます。
BCMによって、事業継続に必要な体制が整備され、組織の危機管理能力が向上することが期待されます。
BCPは、「Business Continuity Plan(事業継続計画)」の略で、災害や危機に備え、事業を継続するための計画を指します。
BCMは、「Business Continuity Management(事業継続マネジメント)」の略で、BCPを実施するためのマネジメントシステムを指します。
安全文化
安全文化は、組織内での安全意識や安全行動を促進し、事故や災害の発生を防止するための文化です。
安全文化には、組織のトップがリーダーシップを発揮し、安全を重要な価値観として組織全体に浸透させることが必要です。
また、社員に対して適切な教育・訓練を行い、安全を実践するための環境を整備することも重要です。
安心
安心は、安全に関する心理的な状態や感覚を表す言葉であり、危険やリスクが存在しない状態に対する感覚です。
安心を感じるためには、物理的な安全性だけでなく、情報やコミュニケーション、人間関係などの社会的要因も考慮する必要があります。
安全と安心は密接に関連しており、安全が確保されることで、人々は安心感を得ることができます。
安全法規
安全法規は、法律や規制などの形で制定され、人や環境の安全を守るために定められた法律やルールを指します。
消防法
消防法は、火災の発生を予防し、火災が発生した場合には速やかに鎮火するための法律です。
消防法には、建物の防火対策や避難経路の確保、火災報知設備の設置、火気の取扱い制限などが規定されています。
危険物 第1類から第6類
危険物第1類から第6類は、国際的に統一された危険物の分類基準です。
危険物には、化学物質や爆発物、放射性物質などが含まれます。
危険物を取り扱う場合には、法律に基づく許可や届出が必要となります。
危険物第1類から第6類までの具体的な例を以下に示します。
- 危険物第1類: 爆発性の物質(火薬、ダイナマイト、火災性ガスなど)
- 危険物第2類: 圧縮ガス(プロパン、酸素、窒素など)
- 危険物第3類: 引火性液体(ベンゼン、アルコール、ペンキなど)
- 危険物第4類: 引火性固体(火薬類、硝酸塩、マッチなど)
- 危険物第5類: 酸化性物質(過酸化水素、塩素酸、塩素など)
- 危険物第6類: 毒性物質(酸化汞、シアン化水素、砒素化合物など)
これらの危険物を取り扱う場合には、法律に基づく許可や届出が必要となります。
また、危険物の取り扱いには、安全対策の徹底や適切な管理が求められます。
高圧ガス保安法
高圧ガス保安法は、高圧ガスの取扱いに関する法律です。
高圧ガスは、爆発や火災などの危険性が高く、安全に取り扱うためには厳しい規制が必要です。
高圧ガス保安法では、高圧ガスの取扱いに必要な安全対策や設備の規格、安全管理体制などが規定されています。
機械の包括的安全に関する指針
機械の包括的安全に関する指針は、機械の安全性を確保するための指針であり、国際的な規格であるISO 12100に基づいて定められています。
機械の設計・製造・販売に関わる人々に向けて、リスクアセスメントの手順や安全基準、安全性評価の方法などが示されています。
消費生活用製品安全法
消費生活用製品安全法は、消費者が安心して製品を使用できるように、消費生活用製品の安全性を確保するための法律です。
消費生活用製品の規格や検査方法、表示表示義務、取り扱い上の注意事項などが規定されています。
製造物責任法(PL法)
製造物責任法(PL法)は、製造業者が製造した製品によって生じた被害について、責任を負うことを定めた法律です。
PL法に基づいて、消費者が安心して製品を使用できるように、製品の安全性に関する規定や責任の範囲、損害賠償請求の手続きなどが定められています。
製品の設計・製造・販売に関わる企業は、PL法に基づく安全対策を講じることが求められています。
PL法は、「Product Liability Law」の略
Safety2.0
Safety 2.0は、従来の安全管理に加えて、人間の行動や意思決定、組織の文化やプロセスに注目し、より高い安全性を実現するアプローチです。
Safety 2.0は、システムアプローチやリスクマネジメントに基づき、組織内でのコミュニケーションや協力、トレーニング、教育などを通じて、個人や組織の学習と成長を促進します。
ELSI(倫理的,法的,社会的課題)
ELSIは、「Ethical, Legal, and Social Implications(倫理的、法的、社会的課題)」の略で、科学技術の発展や導入に伴って生じる倫理的、法的、社会的な課題を指します。
例えば、遺伝子治療や人工知能の導入などによって、個人のプライバシーや人権、社会的な格差や偏見などが生じる可能性があります。
ELSIの観点から、科学技術の発展に伴って生じる課題を洗い出し、適切な対策を講じることが求められます。
5.2 安全に関するリスクマネジメント
(総監キーワード2023より抜粋)
リスクマネジメントは,組織やプロジェクトに潜在するリスクを把握し,そのリスクに対して使用可能なリソースを用いて効果的な対処法を検討及び実施するための技術体系である。
リスクマネジメントのプロセスの中核は,リスク特定,リスク分析,評価と対応であるが,リスクの概念やリスクマネジメントの仕組みは,時代や分野によって変化してきている。
多様な分野のリスクマネジメントを包括するものとして,2009年に ISO 31000が発行され,2018年にその改訂版が発行されている(JIS Q 31000 2019)。ISO 31000では,リスクの影響は好ましいものも好ましくないものも含まれるとしており,経営,品質,環境,安全等の多くの分野を横断して活用されている。
一方,安全分野においてリスクマネジメントを適用する際は,好ましくない影響のみを対象として,重大な被害を受けないための従来のリスクマネジメント手法を活用する場合が多い。
本節では安全分野のリスクマネジメントに関するキーワードを整理している。
リスク管理
リスク分析の前提条件
組織の内外環境の特定
リスク分析を行う前に、組織の内外環境を明確に把握することが必要です。
内部要因としては、人的資源、技術、資金、設備、組織構造、文化などが挙げられます。
外部要因としては、政治的・経済的・社会的・技術的・環境的な要因があります。
これらを把握することで、リスク分析に必要な情報を収集し、分析の基礎を作ることができます。
分析の適用範囲の設定
リスク分析を行う際には、分析の適用範囲を明確に設定する必要があります。
適用範囲は、分析の目的や対象、範囲、期間、精度、評価基準、取り扱い方針などを明示します。
適用範囲を明確にすることで、分析の効果的な実施と分析結果の有用性を高めることができます。
以上の前提条件を満たすことで、リスク分析の準備が整います。
リスク分析は、リスク評価やリスク対応策の策定など、リスク管理において重要な役割を担います。
分析の精度を高めるためには、リスク分析手法の選定や専門知識を持つ人材の参加、情報共有などが必要です。
リスク図
リスク図は、リスク分析において、ハザード(潜在的危険要因)や起こりやすさ(発生確率、頻度)、影響、被害規模、リスク基準などを視覚的に表現するためのツールの一つです。
以下にそれぞれの要素について説明します。
ハザード(潜在的危険要因)
ハザードは、ある事象が発生した場合に、その事象を引き起こす潜在的な要因のことを指します。
例えば、自然災害や人為災害、システム障害などがハザードとして挙げられます。
起こりやすさ(発生確率,頻度)
起こりやすさは、ある事象が発生する可能性の高さを示す指標です。
発生確率や頻度として表現されます。
影響
影響は、ある事象が発生した場合に、その事象がもたらす影響の大きさや範囲を示す指標です。
例えば、人命や財産、環境などに与える影響が挙げられます。
リスクマネジメント計画
リスク図を基に、リスクマネジメント計画を策定することが重要です。
リスクマネジメント計画は、リスクを予防・回避・軽減するための具体的な対応策を示す計画であり、リスク図に基づいて、優先順位や対応の妥当性を検討し、適切なリスク対応策を定めます。
被害規模
被害規模は、ある事象が発生した場合に、その事象がもたらす被害の大きさを示す指標です。
例えば、被害額や死傷者数、地域の被害範囲などが挙げられます。
リスク基準
リスク基準は、リスクを評価するための基準値や基準レベルを示す指標です。
例えば、リスクの許容限界や受容限界、目標リスク値などが挙げられます。
リスクマネジメントシステム
リスクマネジメントシステムは、組織がリスクを適切に管理するために必要な仕組みや手順を定めたシステムのことを指します。
リスクマネジメントシステムは、リスク評価やリスク対応策の策定、リスクモニタリングなどのプロセスを含みます。
具体的には、以下のような要素から構成されることが一般的です。
- リスク管理方針 リスク管理方針は、組織がリスク管理に取り組むための基本的な方針を示したものです。
方針には、リスクマネジメントの目的や原則、責任分担、目標とKPI(重要業績評価指標)などが含まれます。 - リスク管理組織 リスク管理組織は、組織内にリスク管理業務を担当する組織を設置することが必要です。
リスクマネジメント組織は、リスク管理方針に基づき、リスク管理計画の策定やリスク評価、リスク対応策の実施などを担当します。 - リスク評価 リスク評価は、リスクを特定し、そのリスクがもたらす影響や発生確率を評価するプロセスです。
リスク評価には、定量的な評価方法や定性的な評価方法があります。 - リスク対応策の策定と実施 リスク対応策の策定と実施は、リスク評価の結果を踏まえて、リスクを回避、軽減、受容可能なレベルに抑えるための施策を定め、実施することを指します。
- リスクモニタリング リスクモニタリングは、リスクマネジメント計画の実施状況やリスクの変化に対応して、適宜対応策を見直すためのプロセスです。
リスクマネジメント方針
リスクマネジメント方針は、リスクマネジメントシステムを支える基盤となるものであり、組織がリスクマネジメントにどのような方針で取り組むのかを明確にするものです。
リスクマネジメント方針には、リスク管理目的や原則、リスクマネジメントの責任分担、リスクマネジメントの目標とKPIなどが含まれます。リスクマネジメント方針は、組織全体で共有され、リスクマネジメントシステムの実施において重要な役割を担います。
リスクマネジメントシステムを導入することで、組織はリスクを適切に管理し、経営の安定化や企業価値の向上などにつなげることができます。
また、法令遵守や社会的責任の遂行など、組織としての信頼性向上にもつながります。
リスクアセスメント
リスクアセスメントは、リスクマネジメントのプロセスの一つであり、リスク評価を実施するための前提となるリスク特定とリスク分析を含む作業のことを指します。
リスク特定
リスク特定は、組織内および組織外の要因を調査し、リスクを特定するプロセスです。
リスク特定は、内部のプロセスやシステム、人的要因、外部の自然災害や経済状況、競合他社など多様な要因に及ぶことがあります。
リスク分析
リスク分析は、特定されたリスクの影響の大きさや頻度、発生要因などを評価するプロセスです。
リスク分析には、定量的な手法と定性的な手法があります。
シナリオ分析
シナリオ分析は、未来の状況を想定して、リスクの影響度や発生頻度を評価する手法です。
異なるシナリオを想定することで、リスクマネジメント計画の作成や対策策定に役立てることができます。
リスク評価
リスク評価は、リスク分析の結果を基に、リスクの重大度や優先順位を評価するプロセスです。
リスク評価には、リスクマトリクスなどの評価指標を用いることがあります。
対策効果算定
対策効果算定は、実施したリスク対応策がリスクの軽減にどの程度寄与したかを評価するプロセスです。
対策効果算定を行うことで、リスク対応策の改善点や改良点を把握することができます。
リスクマトリクス
リスクマトリクスは、リスクの重大度や優先順位を視覚的に表現したツールの一つです。
リスクマトリクスは、発生可能性と影響の大きさを軸にしたグラフを用いて、リスクを評価するための基準を示すことができます。
リスクの最適化(トータルリスクミニマム)
リスクの最適化は、組織が保有するリスクの総量を最小限に抑えることを目的としたリスクマネジメントの手法の一つで、トータルリスクミニマムとも呼ばれます。
リスクの最適化は、組織全体の視点でリスクを評価し、リスクを減少させるために最適なリスク対応策を講じることを意味します。
リスクの最適化には、リスク対応策の選択や予算の配分、リスク分散などが含まれます。
リスクの最適化は、リスクマネジメントの目的であるリスクを適切に管理し、組織の持続的な発展を実現するために不可欠な手法の一つです。
リスク対応方針
リスク対応方針は、組織がリスクに対処するために採用するアプローチや戦略を示すもので、リスクマネジメント計画に基づいて策定されます。
以下にリスク対応方針に関する説明を示します。
リスク保有
リスク保有は、リスクをある程度受け入れることを意味します。
リスク保有は、組織が適切な対策を講じることができず、対応策がリソース的にも費用対効果的でない場合や、リスクが発生しても組織に大きな影響を与えない場合に採用されます。
リスク低減
リスク低減は、リスクを最小限に抑えるために、対策を講じることを意味します。
リスク低減は、リスクをある程度受け入れるが、それでもリスクを軽減する必要がある場合に採用されます。
リスク回避
リスク回避は、リスクを発生させないために、そのリスクに関する活動を中止することを意味します。
リスク回避は、リスクの発生が組織にとって受け入れがたい影響を与える可能性がある場合に採用されます。
リスク共有
リスク共有は、リスクを複数の当事者で共有することを意味します。
リスク共有は、リスクを回避または低減することが困難な場合に採用されます。
リスク共有には、保険や契約などが含まれます。
リスク対応方針は、リスクマネジメント計画に基づいて策定され、組織の事業戦略、リソース、文化、法律規制などにも影響を受けることがあります。
組織は、自身にとって最適なリスク対応方針を採用することが重要です。
表 リスク保有、リスク低減、リスク回避、リスク共有の定義と事例
| 定義 | 事例 | |
| リスク保有 | リスクをある程度受け入れることを意味し、対策を講じないか、あるいは限定的な対策を講じることを指す。 | 新規事業の立ち上げ時に、競合他社が市場に参入する可能性があることが判明した場合、対策費用をかけずに競合に立ち向かうことを決定した例。 |
| リスク低減 | リスクを最小限に抑えるために対策を講じることを意味し、リスクをある程度受け入れるが、軽減する必要がある場合に採用される。 | サイバーセキュリティ対策として、従業員の教育・啓蒙やパスワードの定期的な変更などを行うことで、サイバー攻撃に対するリスクを軽減する例。 |
| リスク回避 | リスクを発生させないために、そのリスクに関する活動を中止することを意味する。 | 新規事業の立ち上げを検討した際に、市場分析から需要が低くなることが予測された場合、その事業を中止することを決定した例。 |
| リスク共有 | リスクを複数の当事者で共有することを意味し、保険や契約などが含まれる。 | 製造業で使用される原材料の価格変動リスクを、サプライヤーと共有することで、相手先から安定的に原材料を調達できることを確保する例。 |
リスク対応策は、組織の事業戦略、経営資源、リスクマネジメント計画などを踏まえて策定される必要があります。
リスク対応策の選択は、リスクマネジメントの観点から、組織が将来的なリスクに対して、適切かつ効果的なリスク対応ができるよう支援することが求められます。
モニタリング
モニタリングは、リスクマネジメント計画を実施する過程で、リスクの状況や変化を監視することを意味します。
モニタリングによって、リスクが予想以上に高まった場合に適切な対策を講じることができます。
変更管理
変更管理は、組織内で発生する変更に関するプロセスで、変更の適切な実施を確保するための手順や規則を策定することを意味します。
変更管理は、リスク対応策や業務プロセスの改善などの変更が発生する場合に重要な役割を担います。
リスクコミュニケーション
リスクコミュニケーションは、リスクに関する情報を、組織内および外部のステークホルダーに適切に伝達することを意味します。
リスクコミュニケーションによって、組織の信頼性を高め、リスクマネジメントに対する理解と協力を得ることができます。
社会的受容(PA)
社会的受容(PA)は、組織の活動や事業が社会に受け入れられ、承認されることを意味します。
社会的受容を確保することは、組織のリスクマネジメントにおいて重要な課題であり、社会的影響評価などの手法が用いられます。
リスク認知
リスク認知は、組織内の人々がリスクについて認識し、そのリスクに対する適切な対応ができるようにすることを意味します。
リスク認知には、教育や啓蒙、トレーニング、リスク報告システムの導入などが含まれます。
マネジメントレビュー
マネジメントレビューは、組織の経営者や管理職が、リスクマネジメントの状況を定期的に評価するためのプロセスです。
マネジメントレビューによって、リスクマネジメントが組織の目標に対して適切に機能しているかを確認し、必要に応じて対策を講じることができます。
継続的改善
継続的改善は、組織が持続的に改善を進めることを目的としたアプローチで、リスクマネジメントにおいても重要な手法の一つです。
継続的改善によって、リスクマネジメントのプロセスや結果を改善し、リスクを最小限に抑えることができます。
記録の維持管理
記録の維持管理は、リスクマネジメントのプロセスや結果に関する情報を、適切に保存し管理することを指します。
記録の維持管理は、リスクマネジメントの透明性や信頼性を高めるために重要な役割を担います。
ALARPの原則
ALARPの原則は、As Low As Reasonably Practicableの略で、リスクを許容できるレベルに低減することが合理的に可能な限り低減することを指します。
ALARPの原則に基づいて、リスクマネジメントの対策は、コストや社会的受容性を考慮しながら、最適な対応策を講じることが求められます。
As Low As Reasonably Practicable(ALARP)を直訳すると、「合理的に可能な限り低い」という意味になります。
ALARPはリスクマネジメントの分野で使われる専門用語であり、日本語では「合理的な限度内で最低限度」といった意味合いで用いられます。
残留リスク
残留リスクは、リスクマネジメントにおいて取り扱いが難しいリスクの一つで、リスク対応策を実施した後に残るリスクのことを指します。
残留リスクを低減するためには、リスクマネジメントプロセスの再評価や、新たな対策の講じ方を検討することが必要となります。
リスク認知のバイアス
正常性バイアス
正常性バイアスは、過去の経験やデータを基に、何事も正常に進行するものとして、リスクを過小評価してしまう傾向のことを指します。
たとえば、過去数年間に発生した自然災害の被害が少なかった場合、今後も同じように被害が少ないと予想し、適切なリスク対応を講じないことがあります。
楽観主義バイアス
楽観主義バイアスは、何事もうまくいくという楽観的な見方をし、リスクを過小評価してしまう傾向のことを指します。
たとえば、新規事業の立ち上げ時に、成功する確率を過大評価し、リスク対応策を講じないことがあります。
カタストロフィーバイアス
カタストロフィーバイアスは、最悪の事態が起こるという極端な見方をし、リスクを過大評価してしまう傾向のことを指します。
たとえば、新しい製品の開発において、小さな問題が発生した場合に、製品全体が失敗すると予想して、過剰なリスク対応策を講じてしまうことがあります。
ベテランバイアス
ベテランバイアスは、長年にわたってある業務や作業を行ってきたことで、その業務についてのリスクを過小評価してしまう傾向のことを指します。
たとえば、長年同じ製品の製造を行ってきた従業員が、新しい製品の製造に携わる場合、製造プロセスについてのリスクを過小評価する傾向があります。
バージンバイアス
バージンバイアスは、ある分野や業務に未経験であるために、その分野や業務についてのリスクを過大評価してしまう傾向のことを指します。
たとえば、新規事業の立ち上げにあたり、その分野に未経験の従業員がいる場合、分野や業務についてのリスクを過大評価し、適切な対策を講じることができない場合があります。
これらのバイアスによって、リスクマネジメントにおいて、リスクを適切に評価し、対策を講じることが困難になることがあります。
そのため、リスクマネジメントのプロセスにおいては、バイアスを排除するために、客観的なデータや事実に基づいた分析や、異なる視点からの検討を行うことが重要となります。
また、複数のステークホルダーが関わる場合には、意見や意見の相違を明確化することも重要です。
人々は、それぞれのバックグラウンドや経験、文化、認識、知識、信念などによって、リスクに対する認識や評価が異なることがあります。
そのため、同じリスクであっても、関わる人々の視点によって、リスクの表面化が異なることがあります。
たとえば、ある企業にとって、新しい製品の開発に伴うリスクを認識するためには、製品の開発チームや技術者、マーケティング担当者、財務部門、法務部門など、様々な視点を持つステークホルダーが必要です。
それぞれのステークホルダーが、自身の視点に基づいたリスク評価を行い、その結果を共有することで、より全体的なリスクマネジメントが可能となります。
5.3 労働安全衛生管理
(総監キーワード2023より抜粋)
労働安全衛生管理は,組織の運営に伴う災害の根絶を目的とし,職場内の設備,環境,作業方法などを整備し,職場で働く人達の生命や心身の健康を維持するための管理であり,合理的かつ組織的に行われる組織運営活動上の施策である。
組織がその構成員の心身の健康を維持するために,業務上または構内などで発生する災害を防止することや,発生した災害に対しての適切な処置・対策を理解することが重要である。
組織員の保全やモラルの維持高揚に関する対応,心身の健康増進等を対象とする。
労働災害
労働災害は、労働者が仕事中に負傷または病気になることを指します。
これには、事故によるもの、長時間労働やストレスによるもの、または化学物質や物理的な要因によるものなどが含まれます。
災害統計
災害統計は、ある地域や時間帯における災害の発生頻度や種類、被害状況などを集計した統計データのことを指します。
災害統計は、災害対策や危機管理のために役立ちます。
度数率・強度率・年千人率
度数率は、ある出来事が発生する頻度を示す指標で、その出来事の発生回数を対象集団の総数で割ったものです。
強度率は、ある出来事が対象集団のうち一定期間で発生した人数を示す指標で、対象集団の総人数で割ったものです。
年千人率は、ある疾患や出来事が1年間に対象集団の1,000人当たり何人の割合で発生したかを示す指標で、その疾患や出来事の発生数を対象集団の総数で割り、1000を乗じたものです。
災害コスト
災害コストは、災害によって生じる経済的損失を指します。
これには、物的損失(建物や設備の損壊など)や、人的損失(死亡や負傷による医療費や生産性の低下など)などが含まれます。
災害コストは、災害の防止や対策において、財政的な判断材料として役立ちます。
職業病
職業病とは、特定の職業に就いたことが原因で発生した疾患のことを指します。
職業病は、労働者の健康を損なうだけでなく、生産性の低下や財政的負担など、社会全体に悪影響を及ぼすことがあります。
メンタルヘルス
メンタルヘルスは、心身の健康状態に関することを指します。
労働においては、ストレスや過労などが原因で、うつ病や不安障害などの精神障害を発症することがあります。そのため、労働現場においてもメンタルヘルスの取り組みが必要となっています。
労働安全衛生関連法
労働安全衛生関連法には、職場での労働災害や職業病を防止するための法律が含まれます。
具体的には、労働安全衛生法や労働衛生法、産業保健法、消防法、防災対策基本法などがあります。
労働基準法
労働基準法は、労働者と雇用主の権利・義務を定めた法律です。
具体的には、労働時間、休日・休暇、賃金、退職金などが規定されています。
労働安全衛生法
労働安全衛生法は、労働災害の防止や職業病の予防などを目的とした法律です。
職場の安全対策や健康管理、安全教育などが定められています。
労働安全衛生管理
労働安全衛生管理とは、職場において労働災害や職業病を予防するための取り組みのことを指します。
労働者の安全と健康を守ることを目的に、職場環境や作業方法などを見直し、改善することが必要です。
労働安全衛生管理システム
労働安全衛生管理システムは、職場において労働災害や職業病を予防するために、企業が導入するシステムのことです。
具体的には、労働安全衛生の管理体制や方針、目標、計画、実施状況の評価や改善などをシステム的に管理することが含まれます。
労働安全衛生管理システムは、企業における労働安全衛生の向上やリスクマネジメントの強化、法令遵守の徹底などを目的としています。
労働災害や職業病を予防するため、企業が事前に予測できるリスクや危険要因を評価し、それを軽減するための方策を講じることが求められます。
労働安全衛生管理システムの導入には、以下のようなプロセスがあります。
1.労働安全衛生方針の策定:経営陣が労働安全衛生に関する方針を策定します。
2.リスクアセスメント:職場におけるリスクを評価し、改善の必要性や優先順位を判断します。
3.目標の設定:安全衛生の改善目標を定め、達成に向けた計画を立てます。
4.実施計画の策定:具体的な改善策を計画し、実行します。
5.実施状況の評価:計画通りに改善策が進んでいるかを監視・評価し、必要に応じて修正します。
6.継続的な改善:常に改善を継続することで、職場の安全衛生を確保していきます。
以上のプロセスを徹底することにより、労働安全衛生管理システムは、企業にとって労働災害や職業病を防止するための重要な手段となります。
労働安全衛生マネジメントシステム(OSHMS)
労働安全衛生マネジメントシステム(OSHM)とは、労働安全衛生の管理システムのことで、ISO45001という国際規格に基づいたものです。
この規格は、企業が労働安全衛生の管理システムを導入するための指針を提供するものであり、企業の職場における安全・健康環境の向上やリスクマネジメントの強化、法令遵守の徹底などを目的としています。
具体的には、OSHMは以下のような要素を含んでいます。
1.労働安全衛生の方針の策定:経営陣が労働安全衛生に関する方針を策定します。
2.リスクアセスメント:職場におけるリスクを評価し、改善の必要性や優先順位を判断します。
3.目標の設定:安全衛生の改善目標を定め、達成に向けた計画を立てます。
4.実施計画の策定:具体的な改善策を計画し、実行します。
5.実施状況の評価:計画通りに改善策が進んでいるかを監視・評価し、必要に応じて修正します。
6.継続的な改善:常に改善を継続することで、職場の安全衛生を確保していきます。
OSHMは、職場における労働災害や職業病を防止するための重要な手段であり、企業にとって社会的責任を果たすための重要な要素となっています。
OSHMは、「Occupational Safety and Health Management System」の略称です。日本語では「労働安全衛生マネジメントシステム」と呼ばれることが一般的です。
安全衛生方針
法令上、「安全衛⽣⽅針」の表明が明確に義務付けられている訳ではありませんが、一定規模以上の事業場ごとに選任が義務付けられている「総括安全衛⽣管理者」の職務として、「安全衛⽣に関する⽅針の表明に関すること」が含まれています。
「安全衛生方針」はあらゆる安全衛生活動の根幹となるものですので、総括安全衛⽣管理者を選任すべき事業場で有るか否かに関わらず、すべての事業者が表明すべきものであるといえます。
「経営トップによる安全衛生方針の公表」に関するQ&A 厚生労働省
安全衛生教育
労働災害を防止するために、労働者の就業にあたって必要な安全衛生に関する知識等を付与するために実施する教育です。
安衛法59条~60条に規定されています。 労働災害への対策は、設備・作業環境等の整備・改善といった物的対策と、労働者への技能・知識付与や作業マニュアル遵守の徹底といった人的対策に分けられます。
安全衛生教育とは|(一社) 安全衛生マネジメント協会 (aemk.or.jp)
安全衛生管理体制
安全委員会・衛生委員会(安全衛生委員会)
労働安全衛生法に基づき、一定の規模に該当する事業場では、安全委員会、衛生委員会(又は両委員会を統合した安全衛生委員会)を設置しなければなりません。
要件は、下記リンク参照
Q 安全委員会、衛生委員会について教えてください。 (mhlw.go.jp)
共通 3 「総括安全衛生管理者」 「安全管理者」 「衛生管理者」 「産業医」のあらまし | 東京労働局 (mhlw.go.jp)
総括安全衛生管理者
労働安全衛生法第10条では、一定の規模以上の事業場について、事業を実質的に統括管理する者を「総括安全衛生管理者」として選任し、その者に安全管理者、衛生管理者を指揮させるとともに、労働者の危険または健康障害を防止するための措置等の業務を統括管理させることとなっています。
安全管理者
労働安全衛生法第11条では、一定の業種及び規模の事業場ごとに「安全管理者」を選任し、その者に安全衛生業務のうち、安全に係る技術的事項を管理させることとなっています。
衛生管理者
労働安全衛生法第12条では、一定の規模及び業種の区分に応じ「衛生管理者」を選任し、その者に安全衛生業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理させることとなっています。
産業医
労働安全衛生法第13条では、一定規模以上の事業場について、一定の医師のうちから「産業医」を選任し、専門家として労働者の健康管理等に当たらせることとなっています。
安全監査
内部監査は、安全管理体制上の優れた取組及び「事業の安全に関するリスク」を見出し、対応を促すことが目的となります。
さらには、可能な範囲で課題・問題点への対応について提案を行うことにより、安全管理体制の向上が期待できます。
「事業の安全に関するリスク」とは、経営管理側が、事故を惹起させる可能性がある要因と捉え、管理すべき対象と考え対応しているものをいいます。
安全管理体制に係る「内部監査」の理解を深めるために 国土交通省
安全配慮義務
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
・労働契約法(◆平成19年12月05日法律第128号) (mhlw.go.jp)
5.4 事故・災害の未然防止対応活動・技術
(総監キーワード2023より抜粋)
安全管理では,労働安全衛生活動に加えて火災・爆発等の事故や地震等の災害に対応することも重要であり,マネジメントの視点と現場における日常的な活動の視点で考えることが重要である。
事故や災害に結び付く可能性のある事項の抽出,改善策の策定と実施法を対象とする。
不安全状態/不安全行動
「不安全状態」とは、危険な状況や事故が起こりやすい状況のことを指します。
例えば、機械の不調や維持管理の不備、環境の不適切さ、作業者の知識や技能の不足などが原因となって不安全状態が発生することがあります。
「不安全行動」とは、作業者自身が危険な行動をとることで、事故やけがを引き起こす可能性が高くなる状況を指します。
例えば、安全に着座している椅子を使わず、代わりに不安定なものに座ったり、安全帯を着用せずに高所作業を行ったりすることが挙げられます。
ヒューマンファクタ
これらの要因を含めた人間の行動や認知に関する分野を「ヒューマンファクター」と呼びます。
ヒューマンファクターは、作業者の人格的特性、知識、技能、経験、生理的特性、心理的特性、社会的要因などを分析し、作業環境や作業内容に合わせた人間の行動や認知について研究する学問分野です。
これにより、人間の行動を適切に管理し、安全で効率的な作業環境を構築することができます。
ヒヤリハット
「ヒヤリハット」とは、事故や災害などが起こりそうな状況や、事故がほんの少しで起こるところまで行ったが、何とか回避できた状況を指します。
つまり、危険を察知し、それを回避するための行動を取った経験や状況を指します。
ハインリッヒの法則
「ハインリッヒの法則」とは、20世紀初頭にアメリカの保険会社であるトラベラーズ社の技術者であったH.W.ハインリッヒが提唱した、事故の法則です。
この法則は、「大規模な事故の背後には、多数の小さな事故やヒヤリハットが存在する」というもので、一つの事故が発生するためには、それに至るまでの多くの小さな事故やヒヤリハットがあるという考え方を示しています。
ハインリッヒの法則に基づいて、事故を未然に防ぐためには、小さな事故やヒヤリハットを減らすことが重要であるとされています。
つまり、ヒヤリハットを報告し、改善することが、大規模な事故を防ぐために重要であるとされています。
本質的安全設計
製品やプロセスなどを設計する際に、最初から安全性を考慮して設計を行うことを指します。
具体的には、製品やプロセスの構成や素材、設計方法、制御方式などについて、安全性に配慮しながら設計を行うことが求められます。
本質安全化
既存の製品やプロセスに対して、安全性を高めるために、設計や改善を行うことを指します。
既存の製品やプロセスに対して、安全性を追加することを「付加安全」と呼びますが、本質的安全化は、設計自体を改善することで安全性を確保する手法です。
安全防護
事故や災害を未然に防止するために、さまざまな手段を用いて安全を確保することを指します。
具体的には、安全装置の設置、作業者への教育・訓練、危険な作業を行う前のリスクアセスメント、事故報告・調査、安全文化の浸透などが挙げられます。
安全防護は、事故や災害を未然に防止するために欠かせない取り組みであり、本質的安全設計や本質安全化の考え方と合わせて、安全性を確保するために重要な手段の一つです。
システムの高信頼化
システムの高信頼化とは、システムが安全で正常に動作することを維持するために、システム全体に対して、耐障害性を高める設計・構築を行い、高い信頼性を持たせることを指します。
高信頼化は、システムに障害が発生した場合に、それを早期に検出し、システム全体としての信頼性を確保するために行われます。
高信頼化の手法には、冗長性、障害予測・診断技術、信頼性向上設計手法などがあります。
安全計装システム
安全計装システムとは、プラントや工場、航空機、自動車などで、物理現象や化学反応などを測定・検出し、適切な制御を行うための計装システムのことを指します。
安全計装システムには、安全機能を持つ非常停止装置やインターロックなどが組み込まれ、事故の防止や安全性の確保に寄与します。
非常停止装置
非常停止装置とは、工場やプラント、航空機、自動車などで、異常事態や危険な状況が発生した際に自動的に装置や機械を停止させる装置のことを指します。
非常停止装置は、人的なミスや予期せぬ事故を防止するために必要な安全機構の一つです。
フォールトアボイダンス
フォールトアボイダンスとは、システムに障害が発生しても、障害を引き起こす原因を排除することで、システム全体としての信頼性を維持するための技術のことを指します。
例えば、システムに異常が発生した場合にシステムを停止する、異常値を正常値に変換するなどの処理を行います。
フォールトアボイダンス (Fault Avoidance): 障害回避
フォールトトレランス
フォールトトレランスとは、システムが障害を検知しても、システム全体としての機能を維持し続けることができる設計のことを指します。
例えば、二重化システムやトリプル化システムなど、冗長化された機構を採用したり、システム内に障害検知と障害回避のための処理を備えたりすることがあります。
フォールトトレランス (Fault Tolerance): 障害許容
表 フォールトアボイダンスとフォールトトレランスの違い
| フォールトアボイダンス | フォールトトレランス | |
| 定義 | システムに障害が発生しても、障害を引き起こす原因を排除することで、システム全体としての信頼性を維持する技術。 | システムが障害を検知しても、システム全体としての機能を維持し続ける設計の技術。 |
| 目的 | 障害を引き起こす原因を排除することで、システム全体としての信頼性を維持する。 | 障害が発生しても、システム全体としての機能を維持し続ける。 |
| 例 | レイアウトの改善によるケーブルの誤接続の防止 | 二重化システムの導入 |
| 特徴 | 障害の発生を未然に防ぐために、システム自体を改善する。 | 障害が発生した場合でも、システム全体としての機能を維持する。 |
| 対処方法の段階 | 設計段階 | 運用段階 |
フェールソフト
フェールソフトとは、システムの信頼性向上のために用いられる技術の一つで、システムに障害が発生した場合に、その障害に対する軟着陸を行うことで、システム全体としての機能を維持することを指します。
例えば、システムが停止するのではなく、低速化して動作を続けるなどの処理を行います。
フェールソフト (Fail-soft): 軟着陸
フールプルーフ
フールプルーフとは、ユーザーが誤った操作を行っても、それによる危険や不具合を未然に防ぐことができる設計のことを指します。
例えば、電気プラグが差し込まれていない場合に、機械が動作しないようにする、誤った操作をすると鍵が抜けなくなるようにする、といった仕組みがあります。
フールプルーフ (Foolproof): 馬〇でも使える
フェールセーフ
フェールセーフとは、システムに障害が発生した場合に、その障害に対する安全な状態への移行を行うことで、システム全体としての安全性を確保する技術のことを指します。
例えば、リフトやエレベーターなどで、電力が供給されなくなった場合にも、安全な位置で停止する、といった仕組みがあります。
フェールセーフ (Fail-safe): 安全停止
表 フェールソフト、フールプルーフ、フェールセーフの違い
| フェールソフト | フールプルーフ | フェールセーフ | |
| 定義 | システムに障害が発生した場合に、その障害に対する軟着陸を行うことで、システム全体としての機能を維持する技術。 | ユーザーが誤った操作を行っても、それによる危険や不具合を未然に防ぐことができる設計のことを指す。 | システムに障害が発生した場合に、その障害に対する安全な状態への移行を行うことで、システム全体としての安全性を確保する技術。 |
| 目的 | システム全体としての機能を維持する。 | 誤った操作による危険や不具合を未然に防ぐ。 | システム全体としての安全性を確保する。 |
| 例 | 自動車が誤った車線に進入した場合に、ハンドルが揺れるようにする。 | 電気プラグが差し込まれていない場合に、機械が動作しないようにする。 | リフトやエレベーターなどで、電力が供給されなくなった場合にも、安全な位置で停止する。 |
| 特徴 | システムの信頼性を向上させるため、障害に対する軟着陸を行う。 | ユーザーが誤った操作をしても、危険や不具合を未然に防ぐことができる。 | 障害に対して安全な状態に移行することで、システム全体としての安全性を確保する。 |
| 対処方法の段階 | 設計段階 | 設計段階 | 設計段階 |
インターロック(安全装置・安全機構)
インターロックとは、システムの動作に必要な条件を満たすことができなければ、システムの動作を停止する仕組みのことを指します。
例えば、ドアが開いている間に自動車を走行できないようにする、高温になっている炉の扉を開けられないようにする、などの仕組みがあります。
安全確認型システム/危険検出型システム
安全確認型システムは、システムの動作を定期的に監視し、異常が検出された場合には、安全な状態に移行することで、システム全体としての安全性を確保します。
例えば、原子力発電所の制御システムでは、核燃料の状態や冷却水の流量などを定期的に監視し、異常が検出された場合には、自動的に安全な状態に移行する制御機能を備えています。
一方、危険検出型システムは、異常が発生した場合に危険を検出し、システムの停止などの適切な対策を取る仕組みのことを指します。
例えば、自動車のブレーキシステムでは、車速やブレーキの状態を常に監視し、異常が検出された場合には、運転者に警告を表示するとともに、必要に応じて自動的にブレーキをかける制御機能を備えています。
安全確認型システムと危険検出型システムは、異常が発生した場合の対応方法が異なりますが、どちらもシステム全体としての安全性を確保するために必要な技術です。
また、システムの目的や適用される分野によって、どちらを採用するかが異なる場合もあります。
隔離安全/停止安全
隔離安全とは、危険が発生した場合に、その危険を隔離することで安全を確保する手法のことを指します。
例えば、病原菌を含む試料を扱う実験室では、危険な試料と作業者とを完全に隔離することで、安全性を確保します。
一方、停止安全とは、危険が発生した場合に、その危険を察知してシステムを停止することで安全を確保する手法のことを指します。
例えば、自動車における衝突被害軽減ブレーキでは、衝突の危険があると判断された場合に、自動的にブレーキをかけて車両を停止させることで、安全を確保します。
安全立証
安全立証とは、システムやプロセスが安全性を持つことを証明することを指します。
安全立証は、安全性の評価を行うための手法であり、システムやプロセスの設計・開発段階で重要な役割を果たします。
また、安全立証には、信頼性評価やリスクアセスメント、設計文書のレビューなどの手法があります。
LOPA(防護層解析)
LOPA(Layer of Protection Analysis)とは、危険を防ぐために複数の防護層を設けることで、安全性を確保する手法の一つです。
LOPAは、危険の発生原因や発生確率、および防護層の有効性を分析し、必要な防護層を設定することで、システム全体としての安全性を確保することを目的としています。
LOPAは、危険性評価やリスクアセスメントの手法の一つとして広く用いられています。
テクニカルスキル/ノンテクニカルスキル
テクニカルスキルは、具体的な業務内容に必要な技術や知識などの専門的なスキルのことを指します。
一方、ノンテクニカルスキルは、コミュニケーション能力やリーダーシップ能力など、業務において必要な専門知識以外のスキルのことを指します。
例えば、プログラミングの技術はテクニカルスキルに属し、チーム内でのコミュニケーション能力はノンテクニカルスキルに属します。
事故の4M要因分析(Man, Machine, Media, Management)
事故の4M要因分析は、事故が起こる原因を「Man(人)」「Machine(機械)」「Media(材料)」「Management(管理)」の4つの要因に分類して分析する手法です。
この手法は、事故原因を明らかにし、再発防止策を検討するために用いられます。
事故の4E対策(Engineering, Education, Enforcement, Example)
事故の4E対策は、事故防止のための対策を「Engineering(技術的対策)」「Education(教育・訓練)」「Enforcement(法的規制・監督)」「Example(模範的な行動の普及)」の4つの観点から考える手法です。この手法は、事故の予防策を検討する際に用いられます。
5S活動(整理・整頓・清掃・清潔・躾)
5S活動は、職場の効率性や品質向上を目的に、作業場やデスク周りなどの整理整頓、清掃、清潔、規律正しい行動を促す活動のことを指します。
具体的には、「整理」「整頓」「清掃」「清潔」「躾」の5つの工程を通じて、職場の改善を目指します。
小集団活動(ZD運動,改善提案活動,TPM,TQC等)
小集団活動は、職場の改善を目的として、数人から十数人程度の小さなグループで取り組む活動のことを指します。
代表的な小集団活動には、以下のようなものがあります。
- ZD運動:ゼロ欠陥(Zero Defects)を目指して、製品の品質向上を図る活動のことを指します。
- 改善提案活動:職場の問題点や課題を明らかにし、改善策を提案する活動のことを指します。
- TPM(Total Productive Maintenance):設備保全を徹底することで、稼働率の向上や故障防止を図る活動のことを指します。
- TQC(Total Quality Control):品質管理の取り組みを全員の参加で行うことで、品質の向上を図る活動のことを指します。
小集団活動は、職場の現場に密着した改善活動であり、職場の生産性や品質向上に大きく貢献する手法の一つです。
労働災害防止計画
2023年4月から第14次労働災害防止計画が始まります。
「労働災害防止計画」とは、労働災害を減少させるために国が重点的に取り組む事項を定めた中期計画です。
厚生労働省は、中小事業者なども含め、事業場の規模、雇用形態や年齢等によらず、どのような働き方においても、労働者の安全と健康が確保されていることを前提として、多様な形態で働く一人ひとりが潜在力を十分に発揮できる社会を実現に向け、国、事業者、労働者等の関係者が重点的に取り組むべき事項を定めた 2023年 4 月~ 2028年 3 月までの 5 年間を計画期間とする「第 14 次労働災害防止計画」を2023年3月8日に策定しました。
労働災害防止計画について |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
自主保安
自主保安とは、従業員が自発的に安全を意識し、安全な行動をとることを指します。
企業や組織が従業員に対して安全意識の啓発や教育を行い、従業員が主体的に安全対策を推進することが重要です。
未然防止活動
未然防止活動とは、事故やトラブルを未然に防止するために、日々の業務で安全対策を徹底することを指します。
安全対策には、定期点検や点検記録の作成、安全マニュアルの策定、危険予知訓練などが含まれます。
定期点検活動
定期点検活動は、設備や機器などを定期的に点検し、異常がないか確認する活動のことを指します。
点検作業には、点検項目や方法が明確に定められた点検マニュアルや点検シートを用いることが一般的です。
危険予知訓練(KYT)
危険予知訓練は、従業員が日々の業務で危険を予知し、事故を未然に防止するために実施する訓練のことを指します。
危険を予知するためには、事故例やトラブル例などの事例を学び、職場の危険箇所を把握することが重要です。
TBM(ツールボックスミーティング)
TBMは、作業前に行う簡単なミーティングのことを指します。
現場で行う作業に必要な安全に関する情報や注意事項を確認し、作業前に従業員が共有することで、作業の安全性を確保することが目的です。
作業マニュアル
作業マニュアルとは、作業の手順や方法、安全対策などが記載された書類のことを指します。
従業員が安全に作業を行うための情報を提供し、作業の効率化や品質向上にも役立ちます。
安全衛生パトロール
安全衛生パトロールとは、職場に潜在する危険要因を見つけ出すため、職場内を巡視しその結果に基づき機械設備や作業方法などの改善を行うことにより、災害の防止を図るためのものです。
法令で定められた安全管理者や衛生管理者、産業医が行う巡視の他、経営トップや各部署、職場の長などが職場
を巡視し、危険有害な箇所や5Sの状況、作業手順の遵守など安全衛生の管理状況について確認しましょう。
問題が明らかになり指摘を受けたものについては、早急に改善を実施します。
始業前点検
始業前点検とは、作業開始前に機器や設備、職場の状態を点検することを指します。
作業前に異常や故障を発見し、修理や対応を行うことで、安全かつスムーズな作業を実現することが目的です。
点検の内容には、機器や設備の点検や消火器や安全靴の確認、緊急時の対応策の確認などが含まれます。
5.5 危機管理
(総監キーワード2023より抜粋)
危機管理では,危機(crisis)に対する対策のとり方に共通性を見出し,それを体系化し理解することが重要である。
危機管理の対象,危機管理の考え方や手法,危機管理の体系化を対象とする。
危機
危険や困難な状況が迫っており、事態が悪化する可能性が高い状況を指します。
例えば、自然災害や戦争、企業経営の危機などが該当します。
緊急事態
緊急に対応が必要であり、素早い行動が求められる状況を指します。
例えば、火災や地震などの災害、病気や事故による緊急搬送、テロ事件などが該当します。
不測事態
予期しない出来事であり、対応策を事前に準備できない状況を指します。
例えば、経済の変動、不法行為、疾病の蔓延などが該当します。
自然災害(暴風,豪雨,豪雪,洪水,高潮,地震,津波,噴火等による被害)
自然災害は、地球上で生じる自然現象によって生じる災害のことを指します。
例えば、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火などが挙げられます。
これらの自然災害によって、人々や建物、道路、農地などに被害が発生することがあります。
極端化現象
極端現象とは、極端な高温/低温や強い雨など、特定の指標を越える現象のことを指します。
具体的には、日最高気温が35℃以上の日(猛暑日)や1時間降水量が50mm以上の強い雨などです。
気象庁|大雨や猛暑日など(極端現象)の長期変化 (jma.go.jp)
防災気象情報
防災気象情報の活用
気象災害の危険が認められる場所(急傾斜地や渓流の付近、河川や海岸周辺の低地など)に、大雨・暴風・高潮などの激しい現象が加わると、土砂災害・洪水・高潮等が発生し、命に危険が及ぶ非常に危険な状況となります。
このため、対象地区にどのような危険があり、災害種別(土砂災害・洪水・高潮)ごとに、命を守るためにはどのような避難行動をとる必要があるのか(建物からの立退き避難が必要か、建物の2階などへの移動で命の安全を確保できるか)、自治体の公表しているハザードマップやお住まいの地域で過去に発生した災害の記録を参考に、日頃からしっかり認識しておくことが大切です。
土砂災害・洪水・高潮によって命に危険が及び避難行動が必要となるタイミング(判断基準)とエリア(対象区域)の考え方については、内閣府が令和3年5月に改定した「避難情報に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」)において具体的に示されています。
気象庁|防災気象情報とその効果的な利用 (jma.go.jp)
警戒レベル
警戒レベル1~5まで示されています。警戒レベル5は「命の危険 直ちに安全確保」、警戒レベル4は「危険な場所から全員退避」などとされています。
気象庁|防災気象情報と警戒レベルとの対応について (jma.go.jp)
レベル1地震動
原則としてそれが作用しても構造物が損傷しないことを要求する水準を示す。
レベル2地震動
きわめて希であるが非常に強い地震動を定式化したもので構造物が損傷を受けることを考慮してその損傷過程にまで立ち入って構造物の耐震性能を照査する水準を示す。
耐震ガイドライン2章 (jsce.or.jp)
タイムライン
タイムラインとは、災害の発生を前提に、防災関係機関が連携して災害時に発生する状況を予め想定し共有した上で、「いつ」、「誰が」、「何をするか」に着目して、防災行動とその実施主体を時系列で整理した計画です。
防災行動計画とも言います。
国、地方公共団体、企業、住民等が連携してタイムラインを策定することにより、災害時に連携した対応を行うことができます。
タイムライン – 国土交通省水管理・国土保全局 (mlit.go.jp)
避難指示
(ひなんしじ、英: Evacuation Instruction)は、日本の災害対策基本法に基づき、災害が発生した場合に、生命や財産などに被害が発生する恐れのある地域の住民に対して、市区町村長が避難を呼びかける情報のことを指します。
水害、土砂災害、高潮などの災害において、警戒レベルにおいてレベル4の情報(危険な場所から全員避難)に位置付けられています。
避難指示に先立って発表される「高齢者等避難」がある一方、避難指示の発表後に災害が切迫または既に発生している状況で発表されることがある「緊急安全確保」があります。
ただし、避難指示はまだ猶予を持って安全を確保できる段階であるのに対し、緊急安全確保の段階では行動を取っても身の安全を確保できるとは限りません。
2021年5月の災害対策基本法改正により、避難勧告は廃止され、避難指示に一本化されました。
自然災害に起因する産業事故(Natech)
然災害によって引き起こされる産業事故を「Natech(Natural Hazard Triggered Technological)」と呼びます。
これは、自然災害が工場や原子力発電所、石油化学工場などの産業施設に影響を与え、火災、爆発、有毒ガスの放出などの産業事故を引き起こす可能性があることを指します。
例えば、洪水によってダムが決壊し、周辺地域にある石油化学工場に洪水が浸水した場合、化学物質の流出や火災、爆発などの産業事故が発生する可能性があります。
また、地震によって原子力発電所に被害が発生し、原子炉が破損して放射性物質が漏れる事故もNatechの一例です。
Natech事故は、自然災害によって引き起こされるため、事前に防止することが困難であり、被害を最小限に抑えるための対策が必要です。
例えば、産業施設の防災設備の整備や、災害発生時の適切な対応策の策定が必要です。
また、自然災害リスクを評価し、Natech事故の発生を想定した対策を講じることも重要です。
自然災害に起因する産業事故「Natech」 (aist.go.jp)
危険物施設防災
危険物施設は、震災時などには二次被害の発生防止が求められますが、同時に早期の燃料供給や避難支援などの役割が期待されています。
しかし、東日本大震災では多くの危険物施設が被災し、事業の中断を余儀なくされるなどの問題が発生しました。
このため、消防庁は危険物施設の事業者が自らの施設において実施する震災等の対策に取り組むことを支援することを目的として、平成25年度に「東日本大震災を踏まえた危険物施設の震災等対策のあり方に関する検討会」を開催し、「危険物施設の震災等対策ガイドライン」と呼ばれるものを作成しました。
このガイドラインには、過去の被災事例や奏功事例から得られた教訓や、震災後に普及した技術や得られた知見を踏まえた、危険物施設の震災等対策のポイントや留意点がまとめられています。
危険物施設の地震対策には、施設の地盤や建物の強度、安定性の確保、危険物の適切な保管や移動などが挙げられます。
これらの対策を講じることで、危険物施設が地震などの災害に対してより耐性を持つようになることが期待されます。
危険物施設の地震・風水害対策等について | 総務省消防庁 (fdma.go.jp)
原子力防災
平成23年3月11日に発生した東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故を契機に、原子力防災体制の整備の重要性が再認識されました。
内閣府原子力防災担当は、地域の原子力防災体制の充実・強化に係る業務を推進するとともに、原子力防災会議・原子力災害対策本部の事務局機能も含め、関係省庁、関係自治体等との平時及び有事における原子力防災に係る総合調整を一元的に担う組織として、平成26年10月に発足しました。
テロリズム
政治的目的を達成するために、暗殺、殺害、破壊、監禁や拉致による自由束縛など苛酷な手段で、敵対する当事者、さらには無関係な一般市民や建造物などを攻撃し、攻撃の物理的な成果よりもそこで生ずる心理的威圧や恐怖心を通して、譲歩や抑圧などを図ることを目指したものです。
感染症・パンデミック
政府は、新型コロナウイルス感染症危機管理統括庁を設置し、専門家組織を創設することによって、感染症対策の司令塔機能を強化することを表明しました。
統括庁は、感染症対策のエキスパートを育成し、社会経済活動への影響を最小限に抑えるための調整機能を果たすよう努めるべきです。
また、感染症対策に関する国際協力を行い、環境整備にも取り組む必要があります。
日本版CDCを軸にした研究開発の促進には、公衆衛生や感染症対策のサポート、研究開発・生産基盤の確保、そして戦略的研究開発予算の確保が必要とされます。
また、次なる感染症に備えた体制整備も必要であり、現在の医療提供体制のDXが重要であるとされています。
ただし、現在の感染症対策においても改善すべき課題が存在することが示唆されています。
経団連:司令塔機能を強化し、新たな感染症に備える (2022-11-15) (keidanren.or.jp)
危機管理
危機的状況に直面した際、被害を最小限に抑えるために対策を講じることを指します。
危機管理は、災害やテロ事件、感染症の発生など、予期しない事態に備えることが必要です。
危機管理には、予防、対応、復旧、復興などの段階があり、それぞれに対する計画や手順が必要です。
危機管理体制
危機管理に関する組織や体制のことを指します。
組織の大きさや構成は、危機の種類や対象によって異なります。
例えば、国や地方自治体、企業、学校などが危機管理体制を構築する必要があります。
危機広報
危機発生時に、事態を正確かつ迅速に伝え、関係者や一般市民の理解を得るための情報発信活動のことを指します。
危機広報には、報道機関やSNSなどのメディアを使った広報活動が含まれます。
危機管理において、正確な情報の提供が極めて重要であるため、広報活動は危機管理体制の重要な構成要素の一つです。
優先順位
危機管理やプロジェクトマネジメントなどで、複数の課題やタスクに対して、重要度や緊急度などを考慮して、どの順番で取り組むかを決めることを指します。
これによって、リソースや時間の制約の中で、効果的かつ効率的に業務を進めることができます。
危機管理マニュアル
組織が危機に直面した際に、迅速かつ適切な対応をするために、事前に策定しておくマニュアルのことを指します。
例えば、自然災害や人災、テロ事件などに対する対応策をまとめたマニュアルや、感染症発生時における対応策をまとめたマニュアルなどがあります。
マニュアルには、危機管理の体制や役割分担、情報収集・分析、情報発信、対応策の決定・実行、評価・改善などが記載されています。
災害対策関係法等
国民保護法
国民保護法は、正式には「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」といい、武力攻撃事態等において、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活等に及ぼす影響を最小にするための、国・地方公共団体等の責務、避難・救援・武力攻撃災害への対処等の措置が規定されています。
国民保護法とは – 内閣官房 国民保護ポータルサイト (kokuminhogo.go.jp)
災害対策基本法
(目的)
第一条 この法律は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧及び防災に関する財政金融措置その他必要な災害対策の基本を定めることにより、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図り、もつて社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の概要 (bousai.go.jp)
国土強靭化基本法
国土強靱化基本計画について
○強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成25年法律第95号)
第10条に基づく計画で、国土強靱化に係る国の他の計画等の指針となるもの(アンブレラ計画)
○脆弱性評価結果を踏まえた、施策分野ごと及びプログラムごとの推進方針を定める
国土強靱化基本計画|内閣官房ホームページ (cas.go.jp)
ICS(Incident Command System)
ICS(Incident Command System)は、災害や緊急事態の発生時に、効率的かつ迅速に対応するために開発された組織体系のことを指します。
主にアメリカで確立されたものであり、現在では世界中で使用されています。
ICSは、指揮系統を明確にし、各部門や関係機関との連携を円滑に行うことで、より迅速で効果的な対応を可能にします。
また、現場の状況に応じて柔軟に対応することもできるため、様々な災害や緊急事態に対応することができます。
ICSには、主に以下の5つの機能があります。
1.指揮調整(Command)
2.情報作戦(Planning)
3.事案処理(Operations)
4.資源管理(Logistics)
5.庶務財務(Finance and Administration)
安全教育
危機管理における安全教育は、組織内の全従業員に対して、災害や事故が発生した際に適切な行動をとることができるよう、事前に教育を行うことを指します。
具体的には、避難方法や避難場所の確認、救急処置の方法、危険物の扱い方、防災グッズの用意など、災害に備えた基本的な知識や行動について学ぶことが含まれます。
また、危機管理の安全教育には、災害や事故を未然に防ぐための予防教育も含まれます。
例えば、火災を防止するための火気の取り扱いや、地震に備えた家屋の補強、安全に車を運転する方法など、日常生活で実践できる安全に関する知識や技能について教育を行います。
安全教育は、組織内の全従業員に対して定期的に実施することが望ましいです。
教育方法には、講義形式やシミュレーション、訓練などがあります。
また、災害が発生した場合に備えて、緊急時に必要な情報や手順をまとめたマニュアルの作成も重要です。
訓練
訓練は、危機管理において非常に重要な役割を果たします。
主な種類としては、以下のようなものがあります。
事故対応訓練
事故や災害に対する迅速かつ適切な対応が求められるため、想定されるシナリオに基づいた訓練が必要です。
防災訓練計画
防災に関する計画や手順を実践的に確認するための訓練です。
主なものとして、避難訓練、地震・火災・水害等の災害に対する訓練があります。
ブラインド訓練
突然の災害や事故に対応するため、予め準備を行わずに突然行われる訓練です。想定外の状況に対応する力を養うために行われます。
これらの訓練は、実際の事故や災害が発生した場合に、被害を最小限に抑えるために重要な役割を果たします。
また、訓練を通じて、危機管理に携わる人々のコミュニケーション能力や判断力を向上させることができます。
5.6 システム安全工学手法
(総監キーワード2023より抜粋)
システム安全工学手法(故障解析手法,危険シナリオ分析手法とも呼ばれる。)では,リスクの発生過程を調べるために,どのような危険発生源がシステムに存在し,それがどのように事故や災害に進展するかを理解することが重要である。
具体的手法やヒューマンファクタに対する分析手法,システム信頼度解析等を対象とする。
システム安全工学手法
FMEA
FMEA (Failure Mode and Effects Analysis): これは、機械、電子機器、ソフトウェア、またはプロセスなどの製品やサービスの失敗モードとその影響を分析する手法です。
FMEAは、失敗を特定し、重要度を評価し、予防措置を取るための情報を提供するために使用されます。
HAZOP
HAZOP (Hazard and Operability Study): これは、プラント、プロセス、またはシステムの異常操作によって生じる危険性を特定するための手法です。
HAZOPは、プロセスのパラメーターを評価し、システムの弱点を見つけ、危険性を減らすための対策を提案するために使用されます。
HAZID
HAZID (Hazard Identification): これは、プロセスやシステム内の潜在的な危険性を特定する手法です。
HAZIDは、危険性の特定、影響の分析、および対策の提案に焦点を当てています。
デシジョンツリー分析
Decision Tree Analysis: これは、決定を下すために使用される手法であり、特定の問題に対して可能な解決策を評価するために使用されます。
この手法では、さまざまな可能な選択肢が示され、それぞれの結果が分析されます。
最終的な選択は、最も望ましい結果を生み出す選択肢を決定するために下されます。
フォールトツリー分析(FTA)
フォールトツリー分析 (FTA) は、システムの信頼性を評価するために使用される手法であり、システムの障害原因と影響を分析します。
頂上事象
頂上事象 (Top Event): FTA において、分析対象となるシステムの障害や問題の原因となる最上位の事象を指します。
つまり、FTA の分析対象のシステムで最も深刻な結果をもたらす事象です。
最小カットセット
最小カットセット (Minimal Cut Set): 頂上事象を引き起こすために必要な原因の最小集合を指します。
FTA では、システムの障害を防止するために、これらの最小カットセットに基づいてリスクを低減するための対策を決定することができます。
共通要因故障
共通要因故障 (Common Cause Failure): この用語は、複数のシステムコンポーネントに共通の原因によって同時に障害が発生することを指します。
これは、異なるコンポーネントに同じ種類の機能や機能不全がある場合に発生する可能性があります。
FTA においては、共通要因故障を特定して、対策を講じることが重要です。
イベントツリー分析(ETA)
イベントツリー分析 (ETA) は、システムの信頼性を評価するために使用される手法であり、システムの異常事象が発生する可能性を分析します。
以下にそれぞれの用語について説明します。
初期事象
初期事象 (Initiating Event): ETA において、分析対象となるシステムで最初に発生する事象を指します。
つまり、システムの異常事象が発生するきっかけとなる事象です。
防護機能
防護機能 (Safety Function): システムの異常事象を防止または制御するための機能を指します。
ETA では、システム内の防護機能を分析して、システムの信頼性を向上させるための改善策を提案することができます。
ETA は、システムの信頼性評価において FTA と同様に使用される手法ですが、異なるアプローチを取ります。
FTA は、システム内のコンポーネントの障害に着目して信頼性を評価する一方、ETA は、システム内の異常事象の発生に着目して信頼性を評価します。
ボウタイ分析
ボウタイ分析は、システムの失敗とその原因、結果、および対策を明確にするための手法です。
ボウタイ分析は、図形的な手法で、”弓” の形状に見えるため、この名前がつきました。中央の”弓”は、システムの失敗モードを表し、弓の上側は、失敗の原因を表します。
弓の下側は、失敗の影響を表します。
弓の左側は、失敗を防止するための対策を表し、右側は、失敗が発生した場合の対策を表します。
「ボウタイ」とは、システム安全性評価において使用される手法の1つであり、図形的な手法で、”弓” の形状に見えるため、この名前がつきました。
ボウタイ分析は、システムの失敗とその原因、結果、および対策を明確にするために使用されます。
“Bowtie” は、英語で「蝶ネクタイ」を意味します。システム安全性分野においては、「蝶ネクタイ」を形象化した図形を用いて、システムの危険性とその管理方法を分析する手法があり、それが “Bowtie” と呼ばれます。具体的には、中央に “蝶ネクタイ” の形をした図形を配置し、左側には事象の発生原因、右側には事象の結果とその影響、上側には防止策、下側には応急対策を記述して、システムの危険性を管理する手法です。この手法は、リスクマネジメントのプロセスにおいて使用され、危険性を可視化することで、安全性向上につながる対策を講じることができます。
「弓型」という表現は、日本において一般的に使用されるシステム安全性分析の手法の一つである「ボウタイ分析」に由来します。
この手法では、中央に「弓」の形をした図形を使用し、左側には事象の発生原因、右側には事象の結果とその影響、上側には防止策、下側には応急対策を記述して、システムの危険性を管理します。
この手法が「ボウタイ」と呼ばれる理由は、図形的な形状が「蝶ネクタイ」に似ていることからきています。
ただし、日本語での表現としては「弓型」とされることが多いようです。これは、日本語において「ボウタイ」という言葉が一般的でなく、図形の形状が「弓」に近いため、このように呼ばれるようになったのではないかと思われます。
PHA(Preliminary Hazard Analysis)
システムの危険性を評価するための初期段階の手法であり、潜在的な危険性を特定することを目的としています。
PHA は、システムの機能、部品、および関連するプロセスを分析し、危険な要素を特定します。
この手法により、必要に応じてより詳細な安全性評価手法を採用することができます。
PHA は、システム開発の早い段階で使用され、システムの機能を設計段階で改善するための情報を提供することができます。
ヒューマンエラー分析(人的過誤分析)
ヒューマンエラー分析は、人的過誤が原因で発生する事故や障害を分析し、予防する手法の総称です。
人的過誤確率(HEP)
人的過誤確率 (HEP): HEP は、特定のタスクが実行されるときに、人的過誤が発生する確率を評価する手法です。
HEP は、人間工学的な評価に基づいて、タスクを実行するために必要な認知的および身体的要因を評価します。
HEPは、ヒューマンエラー確率 (Human Error Probability) の略称です。
トライポッド理論
トライポッド理論: トライポッド理論は、ヒューマンエラー分析の手法の1つであり、人的過誤が原因で発生する事故を説明するための理論です。
この理論では、事故が発生する原因を3つの足(トライポッド)に分類し、それぞれ「技能」「判断」「状況」の要素があります。
“Tripod”とは、三脚という意味の名詞です。
THERP
THERP (Technique for Human Error Rate Prediction) は、ヒューマンエラー確率を評価するための手法です。
THERP は、作業者の人的過誤が原因で事故が発生する可能性を評価し、安全対策の改善に役立ちます。
行動形成要因(PSF)
行動形成要因は、ヒューマンエラー分析において、人的過誤が発生する原因を分析するために使用されるフレームワークの1つです。
PSF には、作業者の行動に影響を与える要因が含まれており、これによって作業者が誤った判断を行う可能性がある場合に、改善策を提案することができます。
PSFは、人間工学における分析手法である「Preventing Suboptimal Functioning」の略称です。
日本語では「予防的機能低下分析」と訳されます。
MORT
MORt (Management Oversight and Risk Tree) は、管理的な観点から事故の原因を分析するための手法です。
MORt では、管理上の問題によって事故が発生する可能性を評価し、リスクを低減するための対策を提案することができます。
管理・監督・リスクツリー分析(MORT)
J-HPES
J-HPES (Japanese Human Performance Evaluation System) は、日本国内で開発されたヒューマンエラー分析手法です。
J-HPES は、人間の行動と意思決定に着目して、事故を発生させる要因を評価します。
VTA
VTA (Vigilance Task Analysis) は、人間の注意力と認知能力を評価するための手法であり、複雑な作業環境下での人間の認知特性を分析します。
VTA では、注意欠如や疲労、ストレスなどが原因で起こり得るヒューマンエラーを評価することができます。
VTA の結果をもとに、作業環境の改善や運用の見直しなど、ヒューマンエラーのリスクを低減するための対策を提案することができます。
システム信頼度解析
システム信頼度解析は、システムの信頼性を評価するための手法の総称です。
以下にそれぞれの手法について説明します。
信頼性ブロック図
信頼性ブロック図は、システム信頼度解析において一般的に使用される手法の1つであり、システムの信頼性をブロック図で表現します。
信頼性ブロック図は、複数の要素(ブロック)を含み、それぞれの要素が正常に機能する確率を評価して、システム全体の信頼性を算出します。
直列システム
直列システムは、複数の要素が直列に接続されているシステムです。
この場合、システム全体の信頼度は、各要素の信頼度を掛け合わせた値になります。
つまり、直列システムでは、どれか1つの要素が故障すると、全体の信頼性が低下します。
並列システム
並列システムは、複数の要素が並列に接続されているシステムです。
この場合、システム全体の信頼度は、各要素の信頼度の和から、重複している要素の信頼度を引いた値になります。
つまり、並列システムでは、どれか1つの要素が故障しても、全体の信頼性に大きな影響を与えません。
制御システム
制御システムとは、機械やプロセスを自動的に制御するためのシステムであり、様々な産業分野で利用されています。
例えば、自動車や工場の生産ライン、発電所などが挙げられます。
制御システムは、センサーやアクチュエータ、コンピュータなどの要素から構成され、システム内で信号を受け取り、処理を行ってからアクチュエータに信号を送り、プロセスを制御します。
制御システムの中でも、特に重要な機能は、フィードバック制御です。
フィードバック制御では、センサーによって検知された情報をもとに、システムが自己調整し、目標値に合わせた制御を行います。
制御システムにおいては、安全性が非常に重要な要素です。
例えば、自動車の制御システムでは、急ブレーキや急ハンドルなどの操作が必要になった場合に、システムが正しく制御することが求められます。
また、発電所の制御システムでは、万が一の事故に備えて、安全な停止操作が必要です。
そのため、制御システムにおいては、信頼性を確保するために様々な安全対策が講じられています。
例えば、冗長性を持たせることで、システムが故障しても機能を維持できるようにしたり、故障モードの分析を行うことで、問題を事前に予測し、対策を講じたりします。
また、人間工学的な設計を行うことで、操作性を改善し、作業者の負担を軽減します。
最近では、IoTやAIの発展により、制御システムもより高度な制御が可能になりつつあります。
しかし、それに伴い、より高度な技術が必要となり、安全性の確保がより重要な課題となっています。
アクチュエータは、制御システムにおいて、電気信号や液圧・空気圧などのエネルギーを受け取り、機械的な動きを起こす装置のことです。
具体的には、モーターやシリンダー、バルブなどが挙げられます。
アクチュエータは、センサーからの信号を受け取って、制御システムが目的の操作を実現するための動作を行うために重要な役割を担っています。
例えば、自動車のブレーキ制御システムにおいては、アクチュエータが制御システムからの信号を受け取り、ブレーキを作動させることで、車の速度を制御します。
故障モード
故障モードとは、あるシステムが故障したときに発生する問題の種類を指します。
故障モードは、システムの設計や運用上の問題に起因するものや、外部要因によるものなど、さまざまな原因で発生します。
制御システムにおいては、システムの故障モードを分析し、対策を講じることが重要です。
根本原因分析
根本原因分析は、問題が発生した原因を特定し、その原因を解決することで、同様の問題が再発しないようにするための手法です。
根本原因分析には、魚の骨図法や5M分析法など、さまざまな手法があります。
冗長安全
冗長安全は、複数の機能を重複させることで、システムの信頼性を高めるための手法です。
制御システムにおいては、冗長なセンサーやアクチュエータを用いることで、システムの信頼性を向上させることができます。
深層防護
深層防護は、システムの安全性を高めるために、複数の異なるレベルで防護策を講じることを指します。
例えば、制御システムにおいては、論理的な防御策や物理的な防御策を併用することで、システムのセキュリティを強化することができます。
人間工学原則の遵守
人間工学原則を遵守することで、作業者の負担を軽減し、作業効率を向上させることができます。
制御システムにおいては、作業者の負担を軽減するために、適切な表示や操作装置の配置などを行うことが重要です。
また、作業者が操作することが予期しない事態に対応するための手順や訓練を実施することも、人間工学原則の一つです。
これにより、システムの安全性を高めることができます。
制御システムにおいては、これらの手法を組み合わせて、システムの安全性を向上させることが求められます。
具体的には、故障モードの分析を行い、根本原因を特定し、冗長な機能を持たせることで、システムの信頼性を向上させます。
また、深層防護により、システムのセキュリティを強化し、人間工学原則に従った設計や運用を行うことで、作業者の負担を軽減し、システムの安全性を高めることができます。


語句説明&まとめ:総合技術監理
語句説明&まとめ:経済性管理
語句説明&まとめ:人的資源管理
語句説明&まとめ:情報管理
語句説明&まとめ:社会環境管理
PCで見ていただくと目次が追いかけてきてくれます。
技術士会の総合技術監理キーワード集 (mext.go.jp)を見ながら、検索していただくことも可能です。
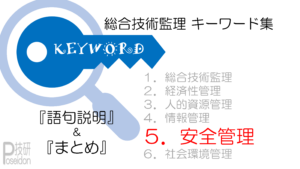



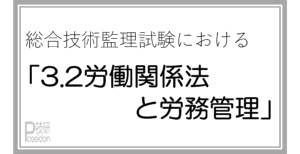


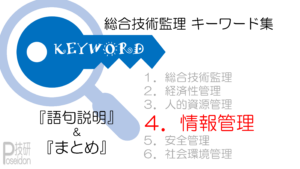

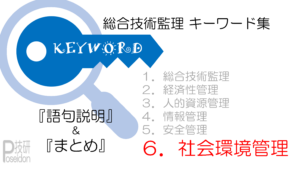
コメント