2022年が終了し、2023年が到来します。
有給などを使われている方は既に休みが始まって、17連休という方も。
ぎりぎりまでお仕事、スタートも4日から、ひょっとすると持ち帰りなどをされる方もおられるかもしれません。
お疲れ様でございます。
令和5年度技術士第二次試験について、概要が発表済みです。
日程等について、確認しておきましょう。基本的に例年通りです。
今日は、これまで勉強してないという人が冬休みの間にできることを書いてみたいと思います。以下、3つです。順不同、どれから始めても構いません。試験テクニック習得ではなく、今後1年ほど続く試験対応のための良いきっかけとする体験を得るためです。
①過去問確認
技術士第二次試験の筆記試験は、過去問が公開されています。
これは、見るだけです。試験項目、解答分量など、どんなことを問われる試験か確認しましょう。
過去問題(第二次試験)|公益社団法人 日本技術士会 (engineer.or.jp)
②sukiyaki塾参照
APECさんによる超有名対策サイトです。私もお世話になりました。
技術士受験を応援するページSUKIYAKI塾 (pejp.net)
1)解答例および合格体験記
参照:二次試験体験記 (pejp.net)
二次試験を終えられた方々による情報提供によるものです。
解答については、原稿用紙にどのように記載しているかなど確認できます。
合格体験記は、これから試験対応に迫られる中で、勇気づけてくれる存在です。
2)試験対策
非常に充実した情報が提供されています。
技術士会からは、模範解答などの情報は提供されていません。
過去の傾向や公表されている情報からその対策が語られています。
非常に充実しています。
3)出願対策
受験願書について (pejp.net)を参照して、③経歴書作成に取り組んでみましょう。
③経歴書作成
令和4年度のデータで作成
令和5年度の提出時には、改めて情報の取得が必要です。
日本技術士会による令和4年度のファイル配布は終了しています。
上記受験願書リンクの情報にあるexcelデータを参照してください。
初めて書かれる方は、1行目から悩むかもしれません。
出願対策の説明を読みながら出結構ですので、一筆目を入れてみて自分の立ち位置を確認してみましょう。
冬休みの時点でかけなくても問題はありません。
それがわかっただけでも、価値のあることです。
この方法の良い所は、ネット環境があればすぐに確認できることです。
合格後は、ペイフォワードの精神を。
冬休みは、家族イベント、友人イベント等でなかなか時間が取れないものですが、隙間時間で結構ですので、手を付けてみてください。
この後の1年間の過ごし方をイメージするにあたり、役に立つ経験となるでしょう。
以上は、ほんの一例です。
本(対策本、白書など)をひたすら読む方もいるし、講師の方とのコミュニケーションで試験対策をされる方がよいという方もいらっしゃいます。
そういう方は、すでに手を動かされているので、この話の対象の方ではありません。
それぞれの方法で、合格という結果に向かい、進んでいきましょう。




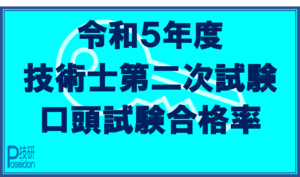
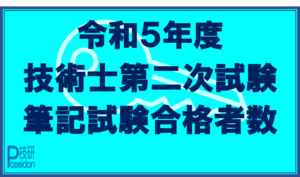
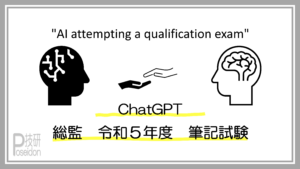
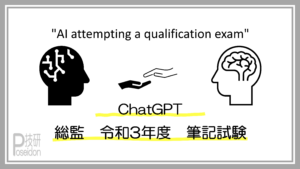
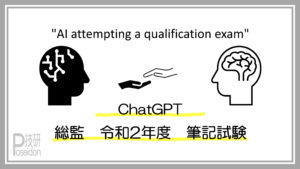
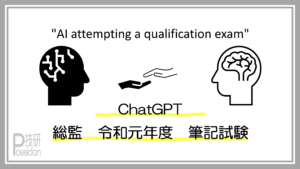
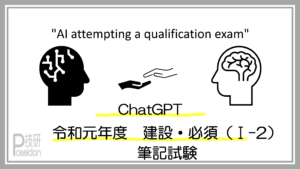
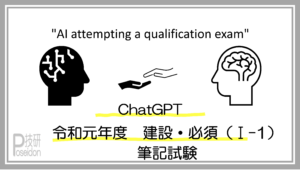
コメント